「では、お願いします。」
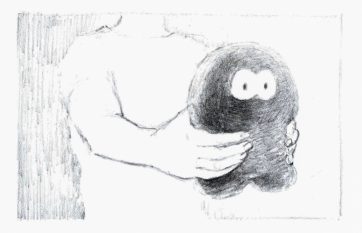
僕は腕の中に抱えていたはてなを差し出した。
白衣を着た人がそれを両手で受け取って、薄汚れた秤にそっと乗せる。

「うーん、残念。もう少しといったところですね。」
「はぁ。そうですか。」
「見た目は大きいのになあ。」
また来てください、の一言を添えて、手馴れた様子で僕のはてなは返される。
「次の方。」
すぐさま別の人が入ってくる。
同じようにして、抱えていたはてなを差し出す。
「よろしくお願いします。」
「はぁい。」
今度のはてなは、ぐるん、と跳ねるように針を傾けた。
「あら、合格ですね。隣の部屋へどうぞ。」
「ありがとうございます!」
合格をもらったその人は嬉しそうに隣の部屋へ向かっていった。
隣の部屋からは何人もの人々の泣き声が聞こえる。しばらくすると、さっきの人の声も混ざりだした。
ここでは、その部屋に入れる人だけが、「 」と言うことを許される。
僕のはてなはまだ足りなかった。
自分ではずいぶん重く感じるんだけど、なんだか中身がないみたいに軽いそうだ。
隣の部屋から聞こえる泣き声は高らかに、堂々とした佇まいでその音を響かせている。
その音を避けるように外に出ると、僕ははてなを抱え直した。


