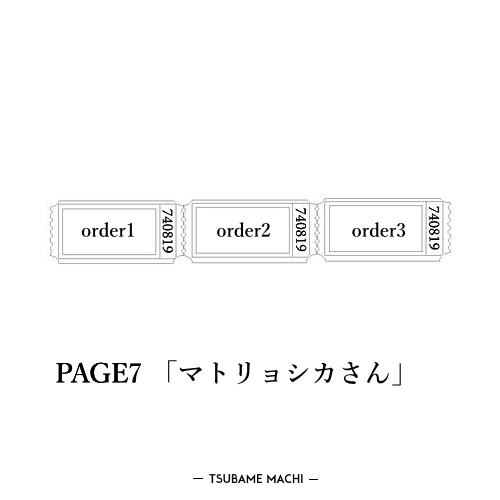(著者注:この作品は第16期から連載しています。初めてご覧になる方は、第16期『ツバメ町ガイドブック PAGE1 「階段オルゴール屋」』からどうぞ!)
世界の片隅の扉の向こうに、その町があり、その指令がある。
”マトリョシカさん”
住所:ツバメ町 A地区 釘の小路
ツバメ町の住民の大半は、旅を知らない。彼らの多くはツバメ扉の内側、つまり自分たちの暮らす町の中しか知らず、”外”に出て行く人はごく稀にいるものの、そういった人はほぼ、町には戻ってはこないという。
人々は、古く狭い石畳、家と店舗を兼ねた小さな建物が密集している路地を、何十年も行ったり来たり、行きつ戻りつ、寄せては返す波が岩壁を削るがごとく、フラットな日常を過ごしているそうだ。だからこそ、ツバメ町には不思議さと奇妙さが住民たち自らの手で供給され続ける。
しかし、渡り鳥たるツバメがシンボルであるツバメ町としては、その強い土着性はいささかその名にそぐわない。ツバメ町から見て”外”にあたる、我々の世界を生きるツバメ達は、自らに快適な気候を求めて、大陸といわず、大海原といわず、何千キロメートルもの距離を横断する。一方、ツバメ町の住民にとってはツバメ町こそが自分たちの基質に適した町で、ゆえに留まり続ける。
けれど、”外”には旅というものがあるらしいと、彼らは知っている。大きなボストンバッグやスーツケースに、何枚もの着替えや寒さを防ぐダウンコートやいざというときに役立つストール、それから化粧道具や、お土産を買う時に便利なエコバッグなど身の回りのもの一式を何もかも詰めて連れまわす旅も、あるいは身体に馴染みきった皮膚のようなジーンズと、第三の手指と化した古い万年筆、あとは己の身体ひとつで往く旅も、その目的はただ一つ、『ここでは見られない何か、触れられない何か、満たせない何かに触れてみたい』ということ。
が、マトリョシカさん、と町で呼ばれている人物はこう語る———
「ツバメ町にいながらにして、旅を作ることは出来るだろうかと考えたのです。だって旅は、きっと良いものなのでしょう? ”外”の人たちは、朝から晩まで、旅のためにせわしなく移動してるというじゃないですか。空を飛んだり海に浮いたりする機械に乗ってまで。あちこち駆けまわるというのがそんなに楽しいのなら、真似してみようと」
太陽も星も空に固定されている、何かの舞台のようなこのツバメ町自体も、絶えず動き続け宇宙を移動し続ける地球という惑星のすみっこに間借りしているのだとしても———。
マトリョーシカ。
その名は”外”ではロシアの名産品であり、大きな人形の中に少し一回り小さな人形が、更にその中にはもうひと回り小さな人形がと、入れ子構造になっている人形を指すが、この町での『マトリョーシカ』はこうだ。
朝、貴方は目が覚める。
簡易宿泊場となっている”六等星をもらえるプラネタリウム”から這い出ると、足元にドロップの缶が一つ、そばにあることに気付くだろう。「落ちている」ではなく、きちんと「置かれている」ふうに。ドロップの缶を開けると、小さな黄色のチケットが出てくる。チケットに書かれているのは、一つの指令。
『水の躍るところへ!』
貴方は寝ぼけ眼でそのチケットを片手に、しばし呆然と黙考する羽目になる。そして思い出すだろう、居住区の南部に噴水の広場があることを。広場へ向かうと、建ち並ぶ家々からは各々の朝食の香りが、雲雀のさえずりのように漂ってくる。貴方の足取りは、軽くも重くもない。待ち受けているのは、更なる謎の気配だからだ。だが町は相変わらず、朝でも薄暗く、薄明るい。ジンジャーエール色の町。
噴水へ辿り着くと、そこには朝早くから活動している様々な人がいる。逆立ちするシマリスを散歩させている人。噴水の水の飛ぶ方向を統計的に割り出している人。人間と同じサイズのキリン相手に何かを熱心に説いている人、長い首で相槌をうつのも大変そうなキリン。独立国家を建設したらどんなお城を建てさせるか、広大な図面を描き続けている人……。どれも奇怪だが、この町ではそのどれもが「普通」の範囲内のような気もして、次なる指令を探し始めると、それはすぐに見つかる。
噴水そばに放置された手押し車の手すりに、真っ赤な風船が括りつけられている。周囲の景色全てが相対的にモノクロに見えてしまいそうなほどに赤い風船。それは微風に揺らぐこともなく、なぜか真っ直ぐに空中で直立している。明らかにこちらに向けて主張しているそれを手に取り、風船の口を縛っている糸をほどくと、中からはまた細長く折りたたまれたチケット。
『心を殺菌してくれる飲み物をどうぞ!』
心を殺菌。意味の分かるような分からないような、抽象的な指令だ。だが生きとし生けるもの、全く殺菌しなくていいほど穢れ無き心を持っているものは少ないだろう。とはいえ、心を殺菌してくれる飲み物とは一体? 方向を指し示してくれそうな風船は、縛る糸をほどいたことでぺしゃんこになってしまっている。風船から続く小川をなにげなく辿るうち、せせらぎの中にきらきら光る瓶を目にする。清流の中で冷やされている、一本のラムネの瓶だ。もちろん、未開封。
起き抜けからこの指令に従って歩きまわる旅をしている空腹な身に、ラムネはありがたい。誰のものでもなさそうなその瓶を冷たい小川の中から掬い上げ、よく冷えたその中身を(周到に近くに配置されていた栓抜きで開封し)飲む。心のくすんだ汚れを洗い流してくれそうな清々しい炭酸水を休み休みしながら飲み干し、改めて瓶を眺めると、瓶の中の青いビー玉の中に、更に小さなメモが閉じ込められている。瓶を割ってビー玉を取り出し、ビー玉に小石を落として割る。小さな小さなメモ。
『風にのる白い子どもたちのところへ!』
こうなると、旅というよりはほとんどなぞなぞだ。答えは……。
風に背中を押されるようにして居住区を抜け行き着くのは、遠くの方には無人の、おそらく廃墟に近い観覧車やメリーゴーランドも見える草原。白い綿毛たちが、さらさらとしたマットな手触りのする風に吹かれながら、けれど風によってというよりはまるで自由意志であるかのような動きで、ふぁあ、と飛び去る。風にのる白い子どもたちとは、たんぽぽの綿毛のことだ。
マトリョーシカは、内へ内へと展開していく人形で、決して外に向かうものではない。けれどマトリョシカさんによって作られた「旅ごっこ」の中で、客は本物の旅を見る。
どこへ向かって旅するんだい。何を見るため旅をするんだい。
問いかけてみても、綿毛たちは言葉も知らないほど、幼い。
だけど、旅をしている。
次号 ツバメ町ガイドブック PAGE8 ─住人のコラム─ 「とある絵描きのエアメール」