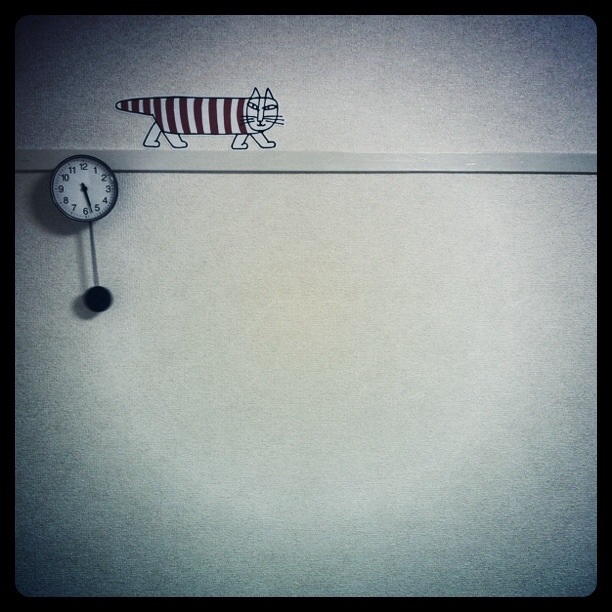
薄いピンクで、1-1から順番に番号がふられている5階建てのマンションに僕たちは住んでいる。冬は早くから朝日が入るのと、夏は直接光が射し込まないのでとても快適だった。そして、ソファに座ると、窓からは空しか見えないというところも気に入っていた。クリスマスが終わった頃に引越しをして、一度契約を更新したから僕は3年半近くここで過ごしたことになる。
部屋は古いけれど真っ白にリフォームされていて、二人で住むにはちょうど良い広さだった。寝室とリビングと少し広めのキッチンがあって、キッチン以外は畳張りの部屋となっていた。僕はリビングの床もフローリングで、天井がもう少し高かったらよかったのにと思っている。もし、そうだったら、お気に入りの本棚も映えるし、いつか手に入れようと思っているあの照明だって合う部屋になるに違いないとよく言っていた。そうすると恋人は決まって「私はこの部屋がすごく気に入っているー。」と畳の上に転がって笑うのだった。そして、僕の気をそらすかのように、その日にあった出来事をはなしだす。
窓から抜ける柔らかい南風とともに、夜は休日へと繋がっていく。
その変化はオンとオフというようなスイッチではなく、ノブやフェーダーで調節するようにとても滑らかだった。
僕らの休日は極端で、一日中家にいることもあれば、仕事が終わってそのまま遠出することもしばしばあった。というのも、日帰りでは短いけれど、前泊するとそれなりの時間が確保できるし、近場の温泉だったらそれで十分だったからだ。それ以外は、必然的に家で過ごすことが多くなり、部屋の居心地と天気の良さは僕たちの休日にとってとても大切になっていた。僕に限って言えば、天気が良い日に家にいるのは、なんとなくもったいない気がしてしまっていたので、諦めのつく雨の休日も悪くないと思っている。ただ、恋人は休みの日に洗濯や布団を干したりできないのは不満らしく、雨の休日はいつも訝しげに空を見つめるのだった。
恋人は掃除と、片付けが得意(もちろん料理もおいしい)で、僕が先に帰ってくると部屋はいつもキレイに整えられていた。そして、部屋の空気はパリッとノリの効いたシーツのように清々しかった。もちろん、そこには空気の不連続性も関係しているのだけれども、それを加味しても余りあるほどだった。
B型の僕にとって「整える」ということは苦手な部類に入る。苦手というよりも気にならないと言った方が正しいのかもしれない。そもそも僕は「このあたり」にしまうのだけど、A型の恋人はしまっておく場所はもちろん、複数持っているものに関しては使う頻度が均等になるよう気にかけているようだった。僕は気に入ったものは毎日のように使うし、モノを選ぶ時のこだわりはあっても、維持することへの執着はなかったから、そういった「大切に使うための決まりごと」はとても新鮮に感じた。そして、そういった自分の中のルールを気づかれないように、自分のペースでこっそり実行しているのは、とても好ましく思えるのだった。
恋人が持っているモノ(といってもとても少ない。)は一つ一つ選び抜かれていて、どれも派手ではないけれど個性があったし、きちんと手入れがされていた。
小さいライオンのキーホルダー。ネイビーのトートバッグ。ボーダーのカットソー。
そのモノからは恋人の空気が放たれていたけれど、ずっと前からこの部屋にあったもののようにピッタリとはまっていた。そんなことを考えていると、自分だけしか知らない空間があるとか、なくなるとかなんてどうでも良いことのように思えた。それよりも、全く異なる環境で生まれ育ち、経験していることも、学んでいることも違うのに、なぜここまで空気感が近くなるのかということの方が興味深かった。次の連休、海で育った僕は、山で育った恋人の住んでいたあの街へいくことにした。



