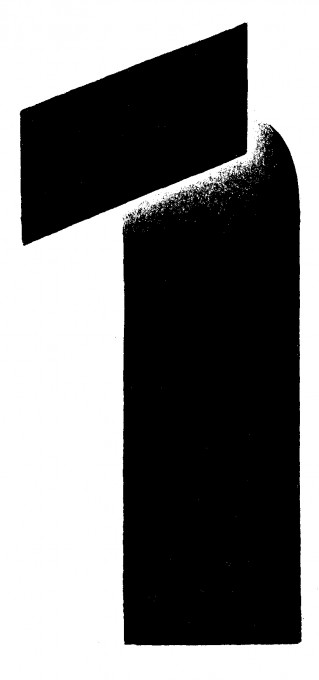
1-1
来なければよかった。何か思いもかけないことがあるかもなんて思わないで、いつも通りに日曜日を過ごせばよかった。
知らない部屋で、知らない人と、また別のよく知らない人を待っている。そっと時計に目をやると二時二十分を過ぎていて、待つこと早十五分。これ、まだ続くのかな。もし今日ここに来ないで、小暮のところに行ってたら。
と考えかけて、それはもうないんだったと思った。あの部屋には、もう行かない。と、頭の中で文字で思って改めて、ああそうなんだなあと思う。自分で決めたことだけど、まだあんまり分かっていない。
物の少ないぶっきらぼうな部屋で、緑子の昔の彼氏だという男の人はさっきから、ボクと緑子とアヤチャンの話をしている。
1-2
「だから彩ちゃんとは、まあ緑子と知り合う前から知り合いっていうか友達で、でも予備校時代から集団でわあっと仲いい感じだったから全然そういう、男女、みたいな感じではなかったんですけど」「あ、そうなんですね」「そうそう。だから僕としては、え、なんで急に? というか、正直よく分かんなかったんですよね。彩ちゃんの気持ちというか、モードみたいなものが」「ああ」「分かんないまま、だけどなんとなく彩ちゃんの中では何かが盛り上がって進行しているみたい、というのは薄々感じてはいて、
1-3
小暮の部屋の冷蔵庫にアボカドがあった。あれはやっぱり、誰か小暮以外の人間によって持ち込まれたものなんだろう。あ、アボカドあるじゃんと私が言って、ああ食べていいよと小暮が言って、え、いいの? うん、俺アボカド嫌いだから。え、じゃあなんであるの? ん? ああ、や、なんか買っちゃって。っていうその続きで、
「え、おかしくない?」
と言えたらよかった。だっておかしいと思う。小暮はけっこう合理的だから。
でも言えなくて、えーわたしアボカドすごい好きーとか言って、食べた。なんでか分からないけど明るくした。本当は丸々一個を一回で食べるのはちょっと多いから、ほんとにいらないの? まあまあ一口だけ、とチャレンジしてそのたびに、いやほんとにいらないからと小暮が言って、(そうでしょ、いらないんでしょう(なのになんであるの))と確認してしまって、一回ごとに、気持ちがもげた。
1-4
ていう状況でとりあえず、すごい勢いで去ってこうとしてる彩ちゃんに対処しようってことになって、『おい、待てよ』ってこう、追いかけて腕をつかむような感じで」「えー、『おい、待てよ!』って? ホントに?」と井尾さんが笑うみたいに言ったので僕も、「そう。いや、まあ今のはちょっとドラマっぽくなっちゃいましたけど」と茶化す感じで言ってしまって「でもそのときに、」その場面を、緑子は遠くから見ていた。僕はそれを知っていた。僕の右斜め前方向にすごい勢いで彩ちゃんが去っていこうとしているのを見ながら、でも女の子の足だし走ったら全然追いつくなと考えて、判断して、走り出す僕を左の遠くの方から緑子がまっすぐ見ているのを見ないようにした。僕が見ないようにしたことを緑子に見られたと思ったそのことも見ないようにした。その一連の感覚が、映画のコマ撮りみたいに残っている。
彩ちゃんはなんで泣いてんだろう。僕は状況に全くついてけてないわけだけど、それと関係なくこの女の子は泣いている、っていうこの「関係なく」とかが冷たいんだろうけど。腕に触れている彩ちゃんよりも、背中の緑子の存在をずっとヴィヴィッドに感じる。
1-5
アボカドは本当に小暮が買ったのかもしれない。小暮は不条理なところもあるから。
問題は本当はアボカドではなくて、そんなこともその時その場で言えない、私と小暮の関係だ。
「それで?」「で、だからそっちの彼女とはまあ一応関係を修復、しまして、でもそのとき取らなかった方の緑子の目が、今思い出しても強かったなぁ……という」「あー。ハイハイ」
と相槌を打つ。傷付いた(であろう)二人の女の人の話を大熊さんが(笑って)話し、私が(笑いながら)聞いて理解を示し、そうすることで私たちの時間が成立する。それと同時に私は、目の前の大熊さんよりよほど、遠くの緑子とアヤチャンに共鳴している。
「ってなんか、すいません。初対面なのにいきなり、すごい自分の話をしてしまって」「いえ別に、そういう昔緑子とどうこう、というのは私は全然関係ないんで、全然気にしていただかなくていいですよ」と言ってから、言葉が少しきつい感じになってしまったかもしれないと思って「正直そんなに仲よくなかったし」と言葉を足して、あ、と思うと案の定、大熊さんはちょっと「え?」という顔をしていた。
「えっと、井尾さんは、高校の同級生だったんですよね?」「や、中高一貫の女子高で」「へえ。じゃあ六年間だ」「はい」
知らない人と時間を過ごさなければいけない状況で、私たちはもう話し過ぎている。といっても大部分は、話していたのは大熊さんだけど、それも私があまり話さないから、気を遣っているのかもしれない。この人ってわりと万遍なく人に好かれそう、と思ってふと、こういう人が緑子と付き合っていたというのは、少し意外な感じがした。
1-6
「でもなんか、ありますよねそういう」「え?」「緑子ってそういう、何も言わないでただジッと見てる、みたいなの、やりそう」「え。あ、そうですか?」「うん、想像できる気がする」「へえ」
井尾さんの言葉の意味がつかみ切れなくて、「なんかほんと、仲良くなかったんですね?」と言ってみた。
「や、そんなこともないですけど」
「はあ」
そんなことも、ないのか。
何だか井尾さんという人は、当たりが強い。でもそれが僕だからなのか、誰にでもなのか、初対面だしわからない。攻撃的というわけではないけれど、感覚が生じてから言葉が出てくるまでの道のりがダイレクトな気がする。
時々、自分は人の気持ちが全然わからない人間なんじゃないかと思う。まあ誰だって思うんだろうけど。そしてさっきから気付かないフリをしてたけど、頭が痛い。
「これってまだ続く感じなんですかね?」
「まあ、お兄さんはまだ飲みたそうでしたよね」
「やー僕、お線香だけ上げてサッと帰る感じかと思ってました」
「大熊さんがけっこう飲むからじゃないですか」
「だって正直、話すことないですもん。……つまみ取ってくるとか言って、遅いすね」
「え、結局何が一番原因で別れちゃったんですか?」
「え?」
予想しなさ過ぎる言葉に一瞬、ブリキみたいになった。オズの。だから緑子との二択で彩ちゃんを取ったってさっき、言ったじゃん。
……と思ったけど、でもそうだろうか?
「その話、戻ります?」
「だって気になるじゃないですか」
うん。そうだね。一度考えてみてもいいかもしれない。井尾さんに話すかどうかは別だけど。
緑子と別れて、だけど彩ちゃんとも、その後すぐにダメになった。僕がフラれた。
思い返せば、緑子に見つめられながら走って泣いたあのときが彩ちゃんの最高潮で、でもその最高潮さに僕は関係なくて、僕を間に置いた緑子との関係の中で彩ちゃんは燃え上がっていたのかもしれない。
いざ付き合ってみたら、僕らは一緒にすることがほとんどなかった。でもそんなのは、誰とだってそうだ。
緑子とは、なんで別れたんだろう。だってまあそうでしょうあの状況では、という浮き島みたいなのが流れてきて乗っかった、以上のことがなかった気がする。その島は僕が呼んだし、でも彩ちゃんも関与してた。
こう考えてみると、僕は何にもあんまりちゃんと関係していない。ただの触媒みたいだ。触媒っていうのは理科の実験とかで使う、自分自身は変化しないんだけど化学反応を促進させるやつ。
「いやいや、でもさすがに、ねぇ」とドアを気にする素振りをすると井尾さんは、「あ、大丈夫ですよ、私見とくんで」とバスケの選手のような姿勢でドアに張り付き「ホラ、早くしないと戻って来ちゃいますよ!」と言い出すので、少し怖いと思った。アルコールが体の中で巡っていて、赤血球を想像する。間違いだけど。早く自分のベッドで横になりたい。
そう思ったところで、大皿いっぱいの餃子を持って、緑子兄が現れた。



