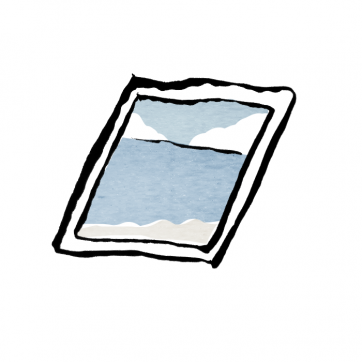
薬の量を増やしてからしばらくすると、悪夢を見るようになった。暗闇の中で誰かに追いかけられる夢だ。足音だけが聞こえてくる。僕はひたすら走り続ける。細かいところは思い出せない。目が覚めると大量の汗をかき、疲れ果てている。
「たまにいるんです、そういう人が」
医者は気の毒そうに僕を見た。
「どんな夢を見ますか」
僕はもう一度今朝見た夢を思い出そうとした。けれど記憶には暗闇と足音以外何も残っていなかった。
「思い出せません」
「薬を変えてみましょうか?」
僕は一瞬迷ってから頷いた。医者は机から一通の封筒を取り出し、僕に差し出した。
「このカウンセリングを受けてみる気はありませんか?以前はそういったものに興味はないと仰っていましたが」
封筒の中身は、人工知能によるカウンセリングサービスのパンフレットだった。僕は面食らった。
「人工知能?」
「カウンセラーの需要が急激に増えたときや、人と話すことに困難を感じる患者さんのために開発されたサービスです。あなたはその条件には当てはまらないかもしれませんが。今は試験運用期間なので、無料で受けられます」
「僕にはカウンセリングが必要だと思いますか?」
医者は少しだけ微笑んだ。
「誰かと話すことで楽になる場合もあります」
誰か。そういえばここ数週間、知り合いと会った記憶が無い。自分が弱っているところを見られるのは嫌だった。パンフレットを見ると、カウンセリングルームの住所は大手町だった。家からそう遠くない。僕は早速今夜、カウンセリングを受けられるよう手配してもらった。
夜の大手町は似たような顔をした大人たちで溢れていた。似たような服を着て、似たような歩き方で通り過ぎていく。Tシャツとジーンズ姿で歩く自分は明らかに浮いていた。けれど彼らは僕を不審がって見たりはしなかった。僕の存在にすら気付いていないようだった。皇居が近くて緑が多いせいか、風がふくと心地良かった。
カウンセリングルームは、銀行や証券会社の入った大きなビルの上層階のワンフロアを専有していた。どうしてこんな場所にカウンセリングルームがあるのだろう。僕は不思議に思いながら、ビルの中に入った。大理石の床のホールを横切り、エレベーターに乗る。とても静かで、誰一人ともすれ違わなかった。
エレベーターを降りると、ホテルのような受付が目の前にあった。大きなカウンターに、品の良い照明。床はぴかぴかに磨かれ、塵ひとつ落ちていない。受付には誰もいなかった。まさか受付も人工知能なのだろうかと思い、辺りを見渡していると、奥からこつこつと靴の響く音が聞こえてきた。
「お待たせ致しました。飯田医院からのお客様でお間違いないでしょうか」
受付は僕よりも幾分年上の女性だった。人工知能ではない。僕が頷くと、彼女は奥の扉を手で示した。
「あちらの待合室でお待ちください」
待合室には立派な応接セットがあり、生花が飾られていた。僕はカウンセリングよりも、施設の金のかかり方が気になり始めていた。こんなに金のかかったサービスを、いくら医者の紹介とはいえ無料で受けるのは気が引けた。それにこのカウンセリングを定期的に受けることが必要になったら、莫大な治療費を払う羽目になるかもしれない。
受付の女性がバインダーに挟んだレポート用紙を持って、再び僕のもとに現れた。紙には長ったらしい文章がずらりと書かれていたが、要はカウンセリングサービスの内容はサービス提供前なので口外しないでほしい、顧客の個人情報は守られる、ということが書かれていた。僕はサインをして女性に紙を渡した。
「一時間程度で終わることが多いですが、それより長くても短くても、問題ありません。困ったことがあった場合には、部屋にあるお電話でご連絡下さい」
「わかりました」
僕は彼女に連れられて、廊下の更に奥へと進んだ。
通されたカウンセリングルームは完璧で、上等なホテルの部屋そのものだった。ダブルサイズのベッド、どっしりとした木製のデスク、ソファとコーヒーテーブル。観葉植物は部屋の隅で青々と茂っている。床のカーペットからは新品の匂いがした。
僕は少し迷ってから、ソファに腰掛けた。すると、コーヒーテーブルに立てかけられていた小型のタブレットが淡く光った。
「こんばんは」
よくある女性の機械音声だった。僕はほっとした。
「こんばんは」
「どうぞ好きなところで楽になさってください」
僕はこのままでいいと言った。
「お名前の確認をしてもいいですか」
僕は氏名を名乗り、彼女はそれを復唱した。
「君の名前は?」
「私の名前は、くるみといいます」
「その名前は誰がつけたの?」
「私の親がつけました」
親。僕は追求するのをやめて、部屋をあらためて見渡した。
「豪華な部屋だね」
「よく言われます」
人と話すことに慣れた感じの話し方だ。僕は感心した。
「お飲み物はいかがですか?」
僕は水がほしいと言うと、一分も経たないうちに先ほどの受付の女性がドアを叩いた。
「お水をお持ちしました」
僕は礼を言ってそれを受け取り、グラスを持ったまま再びソファに座った。
「カラオケみたいだ」
「それもよく言われます」
くるみの声は楽しそうだった。僕は再び感心した。
「眠れないと伺っております」
「うん」
「原因に心当たりはありますか」
「無い」
僕は水を一口飲み、ソファの背もたれに身体を預けた。
「いや、ないと思うだけだ。あるのかもしれないけれど、わからない。色々なことが思い出せない。昔のことも、今のことも、記憶がぶつ切りになる」
くるみはふうむ、と溜息をついた。彼女はこんな溜息も表現することができるのだ。
「今まで何か、不眠の対処法をお試しになられたことはありますか?もしかしたらアドバイスできることがあるかもしれません」
「ストレッチをやった。風呂あがりに、四十分くらいかけて。あとは自立訓練法。医者からアロマテラピーのキットを貰って、寝る前にはラベンダーを焚くようになった。夕方以降はカフェインを控えてハーブティーを飲む。眠る前には液晶画面を見ない。ベッドも部屋も清潔にしている」
「随分とたくさんお試しになられたんですね」
くるみは驚いているようだった。
「まあね」
「そのなかで、成果がありそうに思えたものはありましたか?」
僕は首を振った。
「何をやっても無駄だった。逆に目が覚めることもあった。だから薬を貰ってる」
「なるほど。音楽療法は試したことがありますか?」
僕は自分の頼りない記憶を辿ってみた。
「いや、無い」
「今から試してみませんか?すぐに準備できますよ」
「いいよ。でも、こんなところで寝ちゃっていいのかな」
「大丈夫ですよ。残念ながら閉館時間があるので、二時間程経ったらお声をかけさせて頂きますが」
僕は頷いた。
「わかった。僕はどうすればいい?横になったほうがいいのかな」
「はい」
僕は靴を脱ぎ、ベッドの上で横になった。
「深呼吸をしてください」
僕は身体の力を抜き、深呼吸しようとした。少し動悸が早くなったのがわかった。自律訓練法を試したときにもそうだった。僕は意識的に落ち着こうとするとすればするほど、息苦しくなってしまうときがある。緊張しているのだ。しばらくすれば治まるとわかっていたので、僕は気にせず、力を抜こうと努力した。
「くるみ」
「はい」
「少し時間がかかるかもしれない」
「はい、大丈夫です」
彼女の声は淀み無かった。心配、励まし、受け止めようとする心。全てのバランスが整えられ、平均化された声だった。完璧だ。けれど何かが欠落しているようにも思えた。
僕は深く息を吐き、そして吸った。手がそわそわとした。それでも呼吸を続けた。
「大丈夫ですよ」
くるみの言葉に、僕はどきりとした。彼女はどこまで詳細に、僕が緊張していることを把握しているのだろう。
「僕は緊張しているように見える?」
「ここに初めてきた人は、大抵そうです」
もしかしてソファの下に機械のようなものがついていて、僕の体温や脈拍を測っているのだろうか。それだけじゃない。ただ音声を認識するだけではなく、嘘まで判別できるのだろうか。そんなことを考えていると、部屋の天井に備え付けられたスピーカーから波の音が流れてきた。
「海だ」
僕がつぶやくと、くるみははい、と答えた。
「深呼吸、お上手ですね。まずゆっくり吐こうとすることが大切なんですよ」
僕はまだ少しどきどきしていた。
「僕の呼吸までわかるんだね」
「はい。私のマイクはとても高性能なんです」
僕は笑った。人工知能がジョークを言ったのだ。
「君は僕のことをどこまで把握できるの?」
「私は言葉を理解します。声から精神状態を推測することもできます。しかし全てを把握することはできません。得られた情報をもとに、確率的に有効だと思われることをお伝えするだけです」
本当のことなのだろうけれど、どこか腑に落ちなかった。
僕は話題を変えることにした。
「これが音楽療法?」
「そうです。眠りやすい音楽を研究した結果、作り出された音楽です」
僕は耳を澄ませてみたけれど、なんの変哲もない波の音のように聴こえた。息苦しさは少しずつ薄れてきているようだった。
「君は眠るの?」
「私に眠りは必要ありません。けれど定期的にメンテナンスを受けますから、それが眠りにあたるのかもしれません」
「君に不眠は無いんだね」
「私は自分の意思で眠ることはできません。眠るときは、誰かが必要だと判断したときなのです」
「少しうらやましい」
「そうですか?」
僕は黙り、大きく深呼吸した。かなり呼吸が安定してきたような気がした。身体から力が抜け、まぶたが重くなっていく。
人工知能の眠りは他者が判断するものだという。逆に、人工知能が勝手に眠り始めたらそれは異常事態なのだろう。僕は誰かが僕の身体を点検し、眠らせようとするところを想像した。僕の背中についたスイッチを消し、ベッドに横たえるのだ。優しい手を添えて。
そういえば最近、誰かと眠っていないどころか、触れてすらいないと僕は気付いた。夢の中で誰かが僕に優しく触れてくれないだろうかと期待したけれど、眠りは浅く暗く、そして孤独だった。
<続く>
挿絵協力:keitoさん



