
親しい人にかける言葉が見つからなかったり、信じていたことがぽっきりと折れたり、違和感を感じながら留まり続けたり、2016年は今まででいちばんつらいことが多い1年だった。楽しいことも数え切れないほどあって、それらがなかったらここまで来れなかったかもしれないと考えるけれど、反射的に思い浮かぶのは息苦しい朝だ。
正直、まさか24歳でこんな日々がやってくるとは思っていなかった。高いところで足がすくむ感覚に繋ぎ止められること。心のどこかで、自分はそういう時代は終わったと思っていた。大学を卒業した時、僕は人生が続いていくことを確かに希望として感じたはずだった。でも、この一年は腹をくくらないと進めないことや、これまでに積み上げてきたものへの疑問があちこちで噴き出して、続いていくことの重さを呪っていた。逃げられないわけではなかった。「逃げたい」よりも「あともう少し」を選ぶのは自分なのに、何かに耐えている感覚は拭えず、選ばなかったほうの自分にじっと見られている気がした。
このアパートメントで書いていた文章を読み返しても、なんだかずいぶん遠くへ来たなと思う。3年前の夏、まだ大学生だった頃に書いたもの。良くも悪くも、今の自分には書けない言葉ばかりが並んでいて、恥ずかしくもあり、さみしくもある。
大学生活最後の夏にこの場所で書けたことは、自分にとって大きな、とても良いきっかけだった。いろんな反応をもらったし、その手応えは今の自分の仕事にも繋がっている。
ただ読み返してみると、この時自分はずいぶん背伸びをしていたのだなあと思う。文章に、というより、書いていた自分に対して。今いる場所からの視点のようで、実際はどこか見晴らしのいい場所に上って、そこから見える景色について話しているというか、思想で完結しているがゆえのハッピーエンドという感じ。
それ自体は決して悪いことではないと思う。むしろある年代まで、未来とか世界はそうして語られるものであるだろう。辿ってきた道のりや経験が十分でなくても、自分自身が裏付けでなくても、語ることが許される時期はある。でもそれは可能性や予感でツケ払いしているようなもので、いつまでもできるものではないのだ。
そのことで妙に慎重になりはじめたのも、今年に入ってからだっただろうか。頭でっかちにならず、思想で完結しないものの続きに参加できているだろうか。自分が話したい事柄について、”いつか”の可能性ではなく”今”の経験で話すということが、圧倒的に足りていない気がした。
*
今年はよく本を読んだ。音楽を聴く日もあったけど、社会人になってからはアルバム1枚を聴くためのまとまった時間より、本を数ページ読む細切れの時間のほうが作りやすく、必然的にそちらに流れた。
特に気分が塞いでいた10月、新宿の紀伊国屋で須賀敦子全集の第4巻を買った。須賀敦子の透徹した文体は自分にとってランドマークのような存在で、自分の軸がぶれている時に読み返したくなる。
壮年を迎えてからイタリア文学の翻訳者として注目された須賀は、イタリアで暮らした日々を綴った『ミラノ 霧の風景』を出版すると随筆者としても世に知られるようになる。取り立てて落ち込んでいる人間を励ますような内容ではないが、イタリア、日本、フランスなど、その社会ごとに微妙に異なる光と影を繊細に捉え、そこでしっかりと生きる人間を描いていて、読後には「一人で立つ」ということを思い出させてくれる。
この全集の最初に『遠い朝の本たち』という随筆集が収められている。須賀の遺作であり、著者が病床に伏せながら最後まで推敲を重ねた一冊だ。この中で、須賀は幼少期に夢中になった冒険譚や、大学時代にのめり込んだ世界中の小説といった「遠い朝」に読んだ本の記憶を、時の隔たりを感じさせない細やかな描写で綴っていく。書評や本にまつわる出来事を語るのは須賀の得意とするところだが、その妙は「個人としての読書」と「批評としての読書」の接続の巧みさだろう。批評的な文には個人としての読書が深みを、私的な文には批評としての読書が広がりを与えている。
『遠い朝の本たち』に収められている「クレールという女」という話を読んでいたら、こんな一節があった。
「三人の生き方について、私たちはいったい何時間しゃべりつづけただろうか。共通の世界観とか、自由なままでいるなかでの愛とか、まだほんとうに歩きはじめてもいない人生について流れる言葉は、たとえようもなく軽かった。やがてはそれぞれのかたちで知ることになる深いよろこびにも、どうにもならない挫折にも裏打ちされていなかったから、私たちの言葉は、その分だけ、はてしなく容易だった」
「三人」とは、この中で話題に上る『人間のしるし』という小説の登場人物のことだ。須賀は40年も昔の大学院生の頃に、同級生たちと夢中になったこの本を再び読み解きながら、同時にまだ若かった自分たちのことを振り返る。
フランスの作家クロード・モルガンによって書かれた『人間のしるし』は、第二次世界大戦下のフランスの抵抗運動をモチーフとしている。抵抗運動に身を投じる、自らの信念を持った強い女性・クレールと、そのよき理解者ながら物語の途中で命を落としてしまうジャック、そしてクレールの夫で、優しいが彼女の考えを理解せず、ジャックに嫉妬心を燃やす主人公・ジャンの3人が、物語の主軸を担っている。
自分で選択した生き方を貫いたクレールという強い女性へのあこがれ、ジャンのように優しい男性より、自分の生き方を信じてくれるジャックが夫であってほしいと語った友人の言葉。須賀は3人の登場人物について友人と語り合ったことを昨日のことのようにみずみずしく、かつ恒久的なまなざしで綴る。そこには、嫉妬や妻への無理解といった至らないことの多いジャンへの不信も滲む。ジャンはジャックの死後少しずつ変わっていくのだが、それでも光るような正しさをまとっているのは夭折したジャックだ。
しかし、40年の時を経て『人間のしるし』をもう一度読み直した須賀は、その感想を新たにする。クレールを純粋に愛することだけを考え、生き急いで死んだジャックは「ひとつの思想でしかない」。嫉妬や自己否定を経て、やがて愛することを学んでいくジャンこそ「本当に人生に参加した」人間なのだと。
それが、「深いよろこび」や「どうにもならない挫折」を経て、言葉が「はてしなく容易」ではなくなった壮年の須賀が出した答えだった。
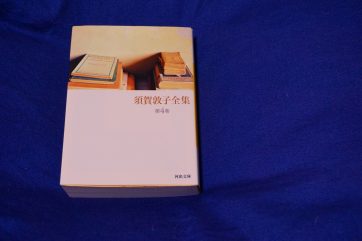
須賀敦子『須賀敦子全集 第4巻』(河出文庫)
*
今、自分は容易な言葉と容易ではない言葉、そのどちらも持て余している。軽い言葉はもう使いたくないけど、人生に裏打ちされた誰かの言葉の前で口を閉ざしてしまうこともまだまだある。ただ、そのことをはっきりと自覚している今、無理矢理にでも「本当に人生に参加」すべき時なのかもしれない。
2016年はアパートメントに編集人として加わることになり、これまで以上に色んな人の文章に触れた。どの文章にもその人の姿が滲み、生きること、生活が続くことの素晴らしさを再確認した。でも、自分のことになると途端に無価値に感じた。それは、ひどく傲慢だったかもしれないと思う。
親しい人にかける言葉が見つからなくても、信じていたことがぽっきりと折れても、違和感を感じながら留まり続けていても、こうして新たな年を迎えようとしている。
今年の逡巡をまとまった文章にすることは避けてきた。答えも救いも生まれないと思ったからだ。でも、そんなもの簡単に生まれないほうが普通なのかもしれない。それなら、普通の記録を残したい。答えも救いもないのに、光の匂いを嗅ぎまわる愚かさも含めて。
冷静な頭では未来のことをいつも思っているし、また会いたい人がたくさんいる。だから人生は続いていく。常にその重さを増しながら。素晴らしさとろくでもなさが、自己嫌悪と自己陶酔がもつれあう。戸惑いながら生き続けろと、自分に言い聞かせている。



