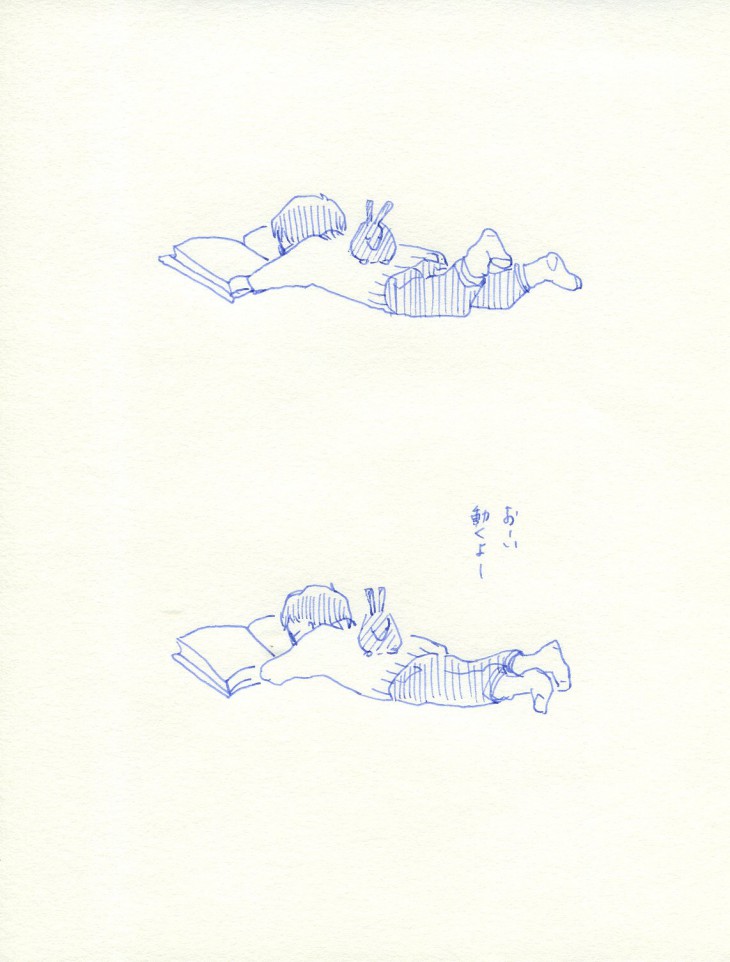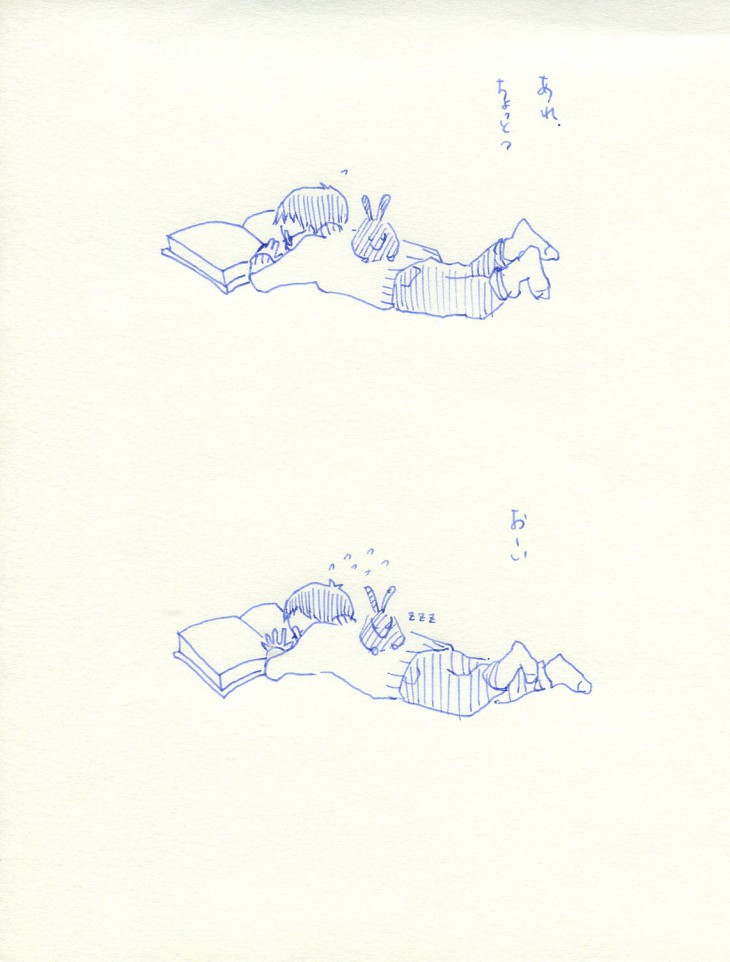雨が降るといつだって、単純なわたしは洗い流してもらったと思う。
アスファルトに成された水の道とたまり場が、こんな凹凸があったのよと両手を広げるよう。
でも今日はその声に応えることもなく、のろのろと歩みをすすめた。
目の前の信号が赤。
横断歩道を前にどこを見ても灰色のビル街の隙間立ち止まる、濡れ鼠。
ぼんやりしていると、たん、と、
透明ビニールの傘越しに女性がわたしを追い越していくのを見る。
わたしより十ほど年上、
急ぎの仕事かな。手にはしっかりとファイルを持って。
寸瞬止まったその背を追うと、
彼女は左右を確認して
すうと右足を大きく踏み出した。
あ
ぱしゃん
心地いい水音が響く。
突然世界にいろ。
安定したパンプスのヒールがみずたまりを大きく踏んで、
女性は軽やかに駆けて行った。
水しぶきが跳ねて、時間がひゅうと引き延ばされる。 ぱたぱたっと みずのつぶ。
だってだってのおばあさん
という絵本の、川を跳び越す頁がめくられて目の前に置かれる。
走り去る背も揺れる髪も、そんなこと考え付きもしなかったと言わんばかりに潔い。
信号が青に変わって、わたしもまた歩き出す。
彼女の残像がわたしの目の前を。
おそるおそる水たまりへ、あと一歩のところで濡れるのを避けて、足は彼女とは別の場へ。
ああ、わたしは五歳になれなかった。
*
*
便り、というのが苦手だ。
連絡を取り続けることができない。
訓練を伴うコミュニケーションの要とも言うべきこれが、わたしには苦痛でたまらない。
急ぎ返答を必要とされている内容が明記されていなければ、そのまま長く置いてしまい、
連絡をくれたことに対する気配りに感謝を示せずに。
手紙や、他愛ない季節のやりとりや、ふとした折に身体の具合はどうかと訊ねること。
ささいな言葉に込められる相手を慮る風。
そういうものに触れるたび、
自分には何かとてつもないものが欠落してしまっているのではないかと、
よぎる不安。
もらうことにばかり慣れてしまっているような。
いたわり、
思いやり、
目には見えない、言葉に置き換えた途端に妙な重みを纏って付箋でもつけたように濃い色を帯びてしまうそれらは、
日常会話のあちこちに、それはそれはひそやかに込められている。
*
言い淀んだ言葉の先を、自分への心配だと思ったのか、
大丈夫だよありがとう、と返されたことがある。
そのときのわたしは実のところ、相手のことなんて目に入っていなくて、
自分の中の心配事を言ってしまおうかと逡巡していたのだった。
心配をかけまいとにっこり笑う彼女を見て、自分が情けなくてなってしまった。
彼女はきっと、逆の立場の時にはわたしの心配をするのだろう。
春の気配がしのびよるように、
自分を中心に全方向へ細かな枝を伸ばすことができたら。
あるいはやわい根を、のばしていくことができたなら。
触れる空気に葉を揺らし、土の個々の隙間を丹念に探る。
散歩の途中に見つけた木の枝が、空に向かうそれがあまりに素直で、しげしげ眺めた。
生き物とは生きるとはこういうことなのですよ、
って、言われてるような。
どこまで近づいて見てもどこまでも、手の抜かれることのない造形。
あたりまえか。
一つ一つ全ての細胞が生きていて、
それぞれに一粒ずつの種の保存をかけて変化していく。
手の抜きようがない、だって、彼らはそれぞれがそれぞれを生きているのだから。
外側から型だけを見ていたことに気づいてひやり。
つぼみに触れる。
鏃のさきのようにとがり、目をこらすと髪より細い、無数の棘。
桜のつぼみが目に入るとこわいからねと言ったのは誰だっけ。
電線にひっかかるからと刈り込むを越えて丸裸にされていた近所の公園の樹の
異様なこぶの盛り上がりが、過去に何度も同じことがあったのですよと話しかけてくる。
異様、と簡単に判断して近づいて、幹から直接生まれた芽に会い、動揺。
*
風の強い夜に、風の強い昼の日を想う。
わたしはその日知らない町を歩いていて、不思議と懐かしい気持ちになっていた。
なんとかして町にひとつの特徴を見いだそうとあれこれと、
隣を歩くひとに言ってみたけれど、反応が芳しくなくやめる。
ここにはここに住むひとの生活があるというただそれだけを、
しばらくたってから思った。
*
わたしはここで、あなたに何を渡せるのだろう?
あなたを大切に思っているのだと、声に、言葉に、
一挙手一投足に織り込んでいられたら。
機織りに並ぶ色とりどりの糸のなかに
たった一本間違いなくひそませていられたら。
わたしが日々編む生活やひととのかかわりや作品という布地の
どこを渡すことになっても
その一本が存在していてくれたなら。
枝葉の先のどのひと垂れにまでそれが、しゅるしゅる通されていたならば。
これまでに手渡された、傑作ともいうべきそれも、つつましやかな柔らかなハンカチのようなそれも、なんだって包める丈夫な風呂敷のようなそれにも、投げてよこした端切れにすら、
それぞれにそれぞれの色と太さでもって、糸は織り込まれていた。
糸巻きそのものを見せるのではなく、
日常の織物のなか、繰り返し繰り返し間違いなく込められた思いが
わたしを支えてくれている。
そういうものを受け取って、
そういうものを渡せるようになりたいと。
話を盛り上げようと取り繕ってぎこちなくなって、
何かが合わなかったり疲れたり
けっしてにこやかで終われないような場面は何度もあって
手に持って渡せぬままでいることもあるけれど
でもいつでも、綺麗とは言えない織り目でそれでも、
それはここにある。
「わたしはあなたに会えてうれしい」
かつて受け取ったそれを
いつかあなたに手渡したい。
*
*
写真の展示を観てギャラリーを後にする。
友人と外へでて傘をさしてから、雨があがったことに気づく。
そういえば捻挫してるんだった。
右足をかばいすぎた左足が痛んで、今日はヒール靴でなかったことを思い出す。
くしゃみをひとつ。
「ここはいつもは猫が多いんだよ」と数羽のカラスの背をみながら彼女が言う。
わたしの知らない晴れの日。
今日という日があるように、今日でない日もずっとある。
わたしひとりぶんの重みを支える足をいまはすこしだけ痛めてしまっていることも忘れずにいよう。
また違う日に五歳になって、きっと水踏むこともある。
今日は元気になれない日。
そういう日だってあるさと、自転車を漕いだ。