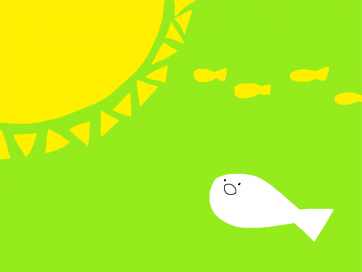トーキョーにはミンミンゼミがふつうにいるので最初の夏はわりと驚いた。それまで住んだことのある土地はアブラゼミとクマゼミばっかりで、ミンミンゼミがいるとすれば山奥の涼しいところ、そうでなければミンミンゼミの声なんてテレビのなかの「夏の演出」にきくばかりだったから。だからトーキョーに夏が来ると、ミンミンゼミをきくと、フィクションにいるような気持ちになります。
都会の夏についてのフィクションなら前に作りました。大学生のとき、わたしは短歌のサークルに入っていた。あるとき京都の短歌サークルの機関誌にゲストとして呼ばれ、「往復書簡」をしたのでした。
往復書簡のなかで、都会は終わらない夏のなかにありました。都会だけ、突然置いて行かれたように夏が終わらなくなって、虫も鳥もどんどん飛び去ってゆき、都会のことを憶えているのはもはや人間だけになってしまう。どういうわけだか魚たちまで空の飛びかたを覚えて去っていく。途中で鳥たちにつつかれたりしながら悲壮に勇敢に飛んでゆくのです。そして植物ばっかり繁茂する。それも、今まであんまりみたことのないような鮮やかな植物ばかりが。みんな諦めて春秋冬服を捨てて、みんな紙を短くして、日中は部屋から出なくなり、夜のお散歩をするひとが増える。会社たちも勤務時間をずらす。都会と都会の外とは季節も生活も噛み合わなくなっていく。都会から出て行ったひともいっぱいいました。北陸の友だちと往復書簡をしたみたいに、都会の外のひとと手紙を送り合ったりすることはできるのに、都会を出て行った友だちとはどうにも連絡がつかないのもおそろしかった。
暑い夏でした。
わたしは冬の寒さがめちゃめちゃ苦手で、夏を楽しみにしているのだけれど、夏が終わらないのはよくなかった。ミンミンゼミが鳴きやまず、その季節が永遠に続く、みたいなかんじの終わらなさはまだ想像できても、セミの声もきこえなくなって、でもずっと夏、というのは、もうよくわからない。
「実家に帰りたいね」と地方出身の友だちとよく言い合いました。
「そうだね、ほんとうに帰れるならだけど」。友だちは悲しそうにする。
「うん。帰れて、そのあとちゃんとこっちと行き来できるならだね」と私も悲しい。
せっかく上京してきたのに、なんでこんなことになっちゃったのだろう。もうこっちにいっぱい友だちがいるし、好きな映画館やラーメン屋があるし、こっちの生活も気に入っているし、夏が続くにしたってここの生活のほうがずっと便利。原因不明の暑さが続くっていうのは確かにヤバい話だけれど、それ自体は慣れちゃえば平気でした。でも、状況がわからなくて、この先どうなのかも不透明で、加えて、可能かどうかはわからないけどとにかくじぶんには都会の外に帰る家があり、そこの家族たちにとても心配されている、っていうのは何重にも居心地が悪い。
「せめてどういうわけなのかが早くわかればいいなあ」
「陰謀論とか、宇宙人説とかじゃなくってね」
「おもしろかったけどね、宇宙人説」
「どうせなら私も連れて行ってほしかったよ、宇宙人め」
ふたりでカウンター席に並んでラーメンをすすっていると、奥のテレビではちょうど「温暖化の影響でしょうか」とかニュースキャスターが話していて、でも誰もそういうそれらしい話は信じません。都会の他は順調に季節を巡らせているようなのに、温暖化の影響だなんて。
「ここだけが変な永遠につかまってしまったみたい」と友だちは唇をぬぐいながら言うので、
「いまの、何かのセリフみたい!」とわたしは茶化す。
事実は小説よりも奇なりです。
でももちろんこれは事実ではないので小説のほうが奇です。
(そうであってねというわたしの気持ちです。)
なお、終わらない夏の都会の出てくる「往復書簡」は下記URLで読むことができます。
http://skazka.o-oi.net/Entry/25/
– – – – – – – – – – –
銀河系少年の日の星めぐり白鳥駅で別れし君よ
/咲耶児『夢糸車』(沖積舎、1989年)
– – – – – – – – – – –