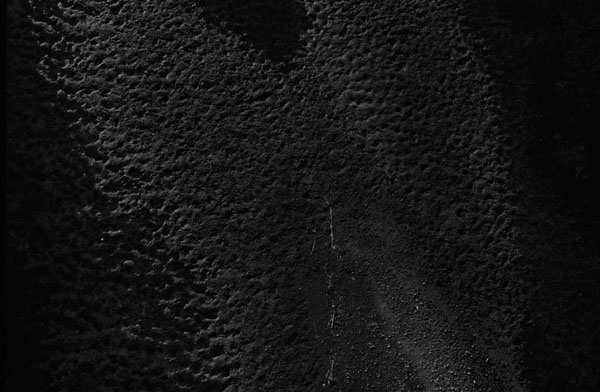強く雨の降る朝、女子学生たちが乗った自転車が十台ほど次々と、全員学校指定らしい同じグレーに赤のラインのレインコートを着て、透明の傘を差して、ゆっくりと僕を追い抜いていった。
じっとり沈んだ湿度の中を、続々と通過していくグレーの集団の後ろ姿が幽玄で映像的にとても美しく、思わず大雨の中足を止めて見送った。
見惚れることしばし、彼女らが雨の向こうに遠ざかってから、あ、カメラ、と馬鹿な顔して僕は突っ立っていた。雨が強かったので、背に負った鞄の中にカメラはしまい込んでいたのだ。
雨にけぶって消えていく背中を見送りながら、最初は「写真には撮れなかったがとても美しい映像を見た」という満足感があった。が、その後ふつふつと、写真に撮れなかったことに対する悔しさが頭をもたげてきた。
この悔しさは写真的な功名心なのではなく、「あの美しさを誰とも共有できない」という意味の悔しさなのだと思う。
僕が絵を描く人であればあの映像をあとからでもキャンバスに定着できるかもしれない。でも写真はそこでシャッターボタンを押さないと何も残らない。雨だからとカメラを鞄にしまっていたのは写真を撮る者としてすでに失格である。
では、僕が女子学生を十人雇い、同じような暗い雨の朝に、写真撮るからゆっくり僕を自転車で追い抜いて行ってくださいと頼んだとして、あの感動的な映像は写真に撮れるだろうか。
どうせろくな写真にならない。撮る僕に、あの映像を見たときの虚 を突かれた感じがもうないから。
写真というのは瞬間の「再現」ではないのだと思う。
世界も僕も準備をしている。その先の唐突な遭遇の上にそれは「降って」くる。
つかみそこねた僕が悪いのだ。

(2011.3 個展『BC』より)