昔、梅田のインド料理屋で働いていた頃の話である。
Bさんというインド人のコックさんと、閉店後の後片付けをしながら話していたのだが、まぁ話していた、と言っても僕は英語が不得手であり、彼は日本語が不得手である。しかもBさん(に限らずインド人コックさんたち)の英語はインド訛りで独特の癖がある。不得手な言語をパズルのように組み合わせながら、なんとか意思の疎通をはかるのだ。
BさんはいつもチーフのMさん(いつも少し横柄)とRさん(日本語が巧みでちょっとお調子者)の間で寡黙にタンドール(壺窯)の前に立っている。どう勘違いもできないくらいに人の好さそうな、色黒の大きな人である。アサヒスーパードライを世界で最高のビールだと絶賛し、インドのインディカ米より日本の米の方が美味しいという。
僕は洗い場のアルバイトとして雇われていたが、カンテ・グランデの厨房で働いている(昼はカンテ、夜はインド料理屋の掛け持ちで働いていた)というと、Bさんは快くナンやプーリーの伸ばし方、焼き方を教えてくれ、店が忙しいときには僕がタンドールの前に立ってBさんを助けてナンを焼くこともあった(今でもナンの手延ばし出来ますよ)。
仕事終りに厨房を清掃しながら、そのBさんと話していたのである。
「カマちゃん、ビスキーソープ、オープン?」
「ビスキーソープ?」
ビスキーとは、おそらくウィスキーであろう。しかしソープとは何か。ウィスキー石鹸とは何か。意味がわからない。
「ワットイズ、ビスキーソープ?」
「ビスキー、ソープ」
身振り手振りを交えても、意味が通じない。ウィスキーの石鹸が開いてるとは何か。何の詩なのか。
30分も悩んだ末に、ようやく「あ! ウィスキーショップ!」
そう、彼は「今の時間、酒屋はまだ開いてるかなぁ」と、たったそれだけのことを聞きたかったのであるが意味が通じず、その30分の間に、もしかしたら開いていたかもしれない酒屋も閉店してしまったのだった。
そのインド料理屋をやめて数年経ったとき、三宮の街なかでバッタリBさんに出会った。懐かしさで即座にハグするくらい再会を喜んだあと、双方笑顔のまま、しかし会話が続かない。
「カマチャン、イングリッシュ、ニガテ」
「うん」
「ワタシ、ニホンゴ、ニガテ」
「うん」
「コミュニケーション、ムズカシネ」
「むずかしね」
お互いに好意を持っているのだけれど、そしてもっとお互いのことを知りたいのだけれど、言葉が通じないというのはどうしようもないのである。お互いものすごくモヤモヤしながら、ニコニコしながら、言葉が通じないなりに表情で思いっきりお互いへの好意を伝え合って、しかしそれ以上はなすすべもなく別れたのである。
このときほど英語ちゃんと勉強しとくべきだったな、と後悔したことはない。
ところで三宮でバッタリ出くわしたBさんと、もし僕が英語が堪能ならば何を話したかっただろうか、ということを考えてみる。
インドから来たという以外に僕はほぼBさんのことを知らないのである。インドに残してきた家族は? 店のオーナーのSってとっても嫌な奴だけど、なぜ長くSの下で働いてるの? オーナーがやたらコックさんたちに高圧的なのは、今でもインドではカースト的な名残があるから? Bさんすごく腕太いけど何かスポーツやってた? スーパードライ最高って言ってたけど、インドではどんなお酒を飲んでた? 僕ら日本人を見てどう思う? あとは、えーとえーと。
知りたいこと、というのは、あらためて頭で考えても、そうそうは出てこない。もちろん会話が続けば、知りたいことは枝分かれして広がっていき、お互いに対する知識は増えていくだろう。好意が深まるかもしれない。しかし僕はBさんのことをろくすっぽ知らないくせに、Bさんに、ものすごく好意を持っている。情報がなくても好き、というこの「好き」の正体は何なのだろう。
これはもう、勘でしかないのだろう。言語の通じる同朋の人の間で培った、人の性格を想像して、実際に答え合わせをして積み上げてきた人に対する好悪の天秤のデータを、言葉の通じにくい人に対しても適応して判断を試みているのだ。そこから理屈が抜けている分、もはや「勘」としか言いようがなく、理屈がないからこそ余計に好意の純度も高いのである。もしかしたら好意に理屈などいらねーのである。
以前ここで『スネ夫問題』*という文章を書いたことがある。人間の性格というものが本当に顔つきだけでわかるのか、というと、本当はわからないと思うし、スネ夫的性格の人間はスネ夫的な顔をしているとは限らない、という話だった。人の本当の性格は顔つきでは読めない。
しかしこの「スネ夫問題」は、本当に悪いやつは悪いやつの顔をしているのか、という話だった。
良い人、といってしまうと話は雑になるが、少なくとも自分と相性がいい人、というのは顔つき、話し方、といった外面的な情報で、かなりの確率で当たるのではないか、と思っている。少なくとも僕はまだ「良さそうな人」が実は良くない人で騙された、という目には遭ったことがない。僕は単に運がいいだけなのだろうか。それとも何か特殊な嗅覚のようなものが働くのだろうか。嗅覚なのだとしたらそれはなかなか誇るべき才能な気がするのだが。
もしBさんがまだ日本におり、また三宮で偶然再会したとしたら、またハグして喜んで、そして会話に困って「むずかしね」と別れるのかな。僕は相変わらず英語できないし、なんとも進歩のない話である。
でも会いたいなぁBさん。5分でバイバイするとしてもね。
・・・・・・
余談であるが、Bさんといえば、ここ(アパートメント)とは別の場所に以前こんな話を書いたことがある。読んだことない人もいると思うから抄録する。
このインド料理屋に、”辛いもの食える自慢” の男がやってきて、この店で一番辛いカレーを出せと言う。
Bさんは困った顔をしながら、とりあえずホットチキンという、一番辛いメニューを出す。しかし男は「なんや、たいしたことないな。全然辛くないやんけ」と文句をいい、明日また来るからもっと辛いカレーを用意しろ、と言って去る。
「アンナ客、嫌イ」
Bさんは不機嫌である。そりゃそうだ。辛いだけがインド料理ではない。辛さ自慢ならハバネロソースでも丸呑みしてればいいのである。辛さの下にある味わいなんか、ああいう男はどうでもいいのであろう。
翌日また来たその男に、唐辛子を5倍量入れたホットチキンを出すが、男は「全然や!」と嘲って、明日こそ頼むで、と帰っていった。
温厚なBさんも腹を立て、それ以上にバイトの僕が激昂した。
明日のカレーの味付けは僕にさせてほしい。そうBさんに頼んだ。
はたして翌日また男がやってくる。
「今日こそ期待してるで」
こういう男は唐辛子の辛さに鈍麻しているので、いくら唐辛子を放り込んでもきっと効かないのである。Bさんがいつもの10倍ほど唐辛子を入れたホットチキンを作り、そこに僕は一掴みの塩を投入してその男に出した。
唐辛子への耐性は出来ても、人間は塩の過度の辛さには耐えられないと思ったのである。
男は目を白黒させながらカレーを食べ、大汗をかいて、
「きょ、今日のはなかなか手強かったわ・・・」
と言って帰っていった。僕とBさんはガッチリ握手をした。
もちろんその後、男は二度と店に現れなかった。







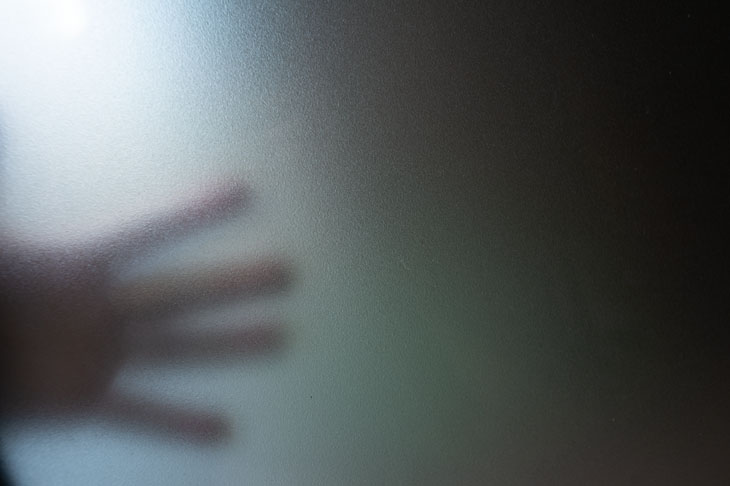


*)『スネ夫問題』



