iii 柔らかい水

小指の爪ほどに小さく見える、はるか遠くの山から太陽が昇る頃。
インベーダーゲームの電子音のような声で話すおじさんに連れられて、私は「なんきょくじん」と呼ばれる人々の住む街へ到着した。
等間隔で行儀良く並んだ建物はどれも角砂糖そっくりの真っ白な立方体をしていて、角砂糖工場の中へ迷い込んだかのようだった。私はすぐに近くの建物の中へ案内された。
そこは小さな病院らしかった。待合室は暖炉の炎で隅々まで温められていて、一歩足を踏み入れた途端に体に降りていた霜が融けて行くのを感じた。おじさんは受付の女性に例の電子音に似た言葉で声をかけた。何を言っているのかは分からないけど、私の事を説明しているんだろうという察しはついた。
そばにあった長椅子に腰掛けて、学校で見ていたのと同じ色をした天井をぼんやりと眺めていると、女性に銀色の湯気の立つマグカップを差し出された。
無色透明だったので白湯かと思ったら、薄荷ドロップのような味がした。これは何という飲み物なんだろう。
葛湯のようなとろみと優しく仄かな甘さに夢中になって、喉を火傷しそうになりながらも、喉を鳴らしてあっという間に飲み干してしまった。
ほう、と吐いた息も手の中のカップと同じ温度まで上がっていた。
それから女性看護師さんに連れられて、診察室へ通された。多分凍傷がないかを診てくれるのだろう。
おじさんは笑って見送るだけで、ついて来てはくれなかった。
色彩の少ない室内に置かれた家具や道具は、どれも見覚えのあるものばかりで(本やポスターに書かれた文字は不可解なデザインだったけど)それを見る限りでは、知らない言葉を話す人の住む街へ来たという実感は湧かなかった。
待っていた院長らしき先生は、保健室の先生に雰囲気がとてもよく似ていた。やっぱり別の国の人、という印象は全く無かった。だけど看護師さんと交わしている言葉はおじさんと同じく不可解なもので、二人の声はガムランボールやオルゴールや、おもちゃのピアノの音を連想させた。
確かに女性らしい声ではあったし、とても綺麗だと思った。けれどもそれを聴いていると、意思の疎通は絶対に無理だろうという不安が、胃の中で更に膨れ上がった。
こんな気持ちで音楽を聴くのは初めてだ。
そんな不安が顔に表れていたんだろうか、院長先生は目が合うと微笑んだ。そして口を開いた。
「さっきの飲みっぷりからして、凍傷は軽いものだったみたいね」
日本語だ。
所々古いスピーカーを通したようなノイズが混じっているものの、おじさんよりももっと流暢だった。
「はい」
体が温まったお陰か、掠れていた声は元の湿度を取り戻していた。
「話せるんですね」
院長先生は笑った。
「あなたもね。この街で北半球の言葉が話せるのは、私と夫だけなの」
「ご夫婦だったんですね」
先生は私の左腕を取って観察しながら答えた。
「私が教えてるの。旦那はまだ勉強し始めたばかりだから、まだまだこれからね。ごめんなさいね、驚かせてしまって——はい、口開けて」
「いえ、あのままだったらきっと凍死してました」
そう言って口を開いた。先生がペンライトで喉彦を照らす。
「あーん。うん、大丈夫そうね。はい、次は目ね。じっとしてて」
両目蓋に指を添えられ、青白い光を当てられる。収縮した瞳孔を見る先生と目が合う。彼女の瞳は僅かに青みがかった濃い灰色をしていた。
「充血が酷いわね。白目が全部真っ赤になってるわよ。痛みは?」
「今は大丈夫です。さっきまでは痛かったんですけど、ここへ来た時にはもう治まって」
私はここへ来るまでの事を説明した。目の痛みと発熱のこと、学校の保健室にいたこと、オーロラのように光るカーテンのこと、それをくぐったらここに放り出されたこと。先生は黙ってそれを聞いていた。話が一通り終わると、顎に手を当てて唸り声を上げた。
「私、帰れるんでしょうか」
「うーん、断言してあげたいけど、まだ無理ね。でも、ここへ来たのが突然だったように、突然何かの拍子に帰れるかもしれない」
先生は椅子から立ち上がって、壁に貼られた南極大陸の地図を見た。そして大陸の中心に近いある一点を指さした。
そこには赤十字に似た、だけど星のようにも見える形のマークが濃紺で刷られていた。
「私達が今居るのが、ここ。海の港までは1000km以上ある。この近くに空港はない。車はあるんだけど、この街の人はみんな使いたがらないからエンジンは完全に凍ってて使えなくなっちゃってる。だから、自分の足で帰るのは無理だと思う」
聞かされた事実を受けても、不思議なほど心は平静を保っていた。あの飲み物を飲んだせいだろうか、目の痛みがないせいだろうか、この人には言葉が通じるからだろうか。それとも、ここにはいつも煩わしく思っていた余計な音や声や、色がないせいだろうか。
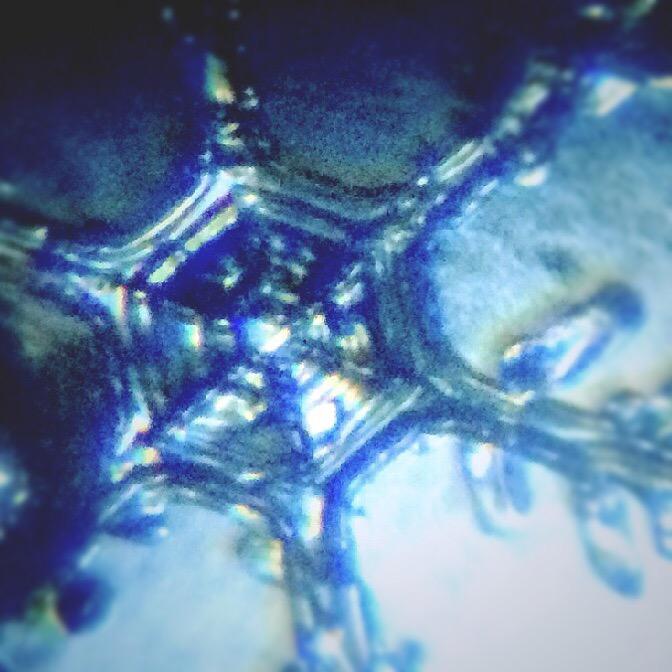
うつむいて黙り込んでいるのを不安がっていると思ったのか、先生は私の肩を何度も叩いて笑った。
「大丈夫よ、それまでは私のところで面倒見てあげるから! あなたは私の患者だし、患者を診るのが私の仕事」
顔を上げて私は早口に尋ねた。
「あの、」
「ん?」
「どうしてそこまでして下さるんですか? 私、診察代を払うお金も持ってないのに。お仕事なら、対価が必要でしょう?」
小さじ一杯分の沈黙。彼女はすぐには答えなかった。
「むかーしの話よ。この街にもね、一人だけやって来たことがあるの。北半球の国の人が」
「私と同じように?」
「いいえ。その人は北半球からこの大陸に移り住んだ人でね。ここからずっと離れた所に自分の研究所を作って、たった一人で住んでいたの」
頭の中に、ベッドへ置き去りにしてきてしまったあの白い本が浮かんだ。偶然の一致だろうか。
「ひょっこりここへ迷い込んできてね、それから3ヶ月くらい居座ってたかな。私は…ううん、この街の人はみんなその人にお世話になったから。それが、あなたを居候させる理由!」
居候、という最後の言葉に私は思わず吹き出した。先生も笑った。ひとしきり笑って、私は言った。
「先生、この街の事をもっと教えて下さい。『なんきょくじん』の事も、あと言葉も」
「じゃあ、まずは着替えなくちゃ。その格好だとまた凍っちゃうし。家の事も説明しないと」
と、私に麻製の大きな手提げ袋を手渡した。
「着替えたら出てきてね。待合室で待ってるから」
中には白のブラウスと、暖かそうな淡いブルーグレーのジャンパースカート、厚手の白い靴下、薄灰色のフード付きコートが入っていた。サイズはどれも誂えたかのようにぴったりだった。
診察室から出ると二人が出迎えた。
「あら、似合うわね。さすが私の見立てね。寒くはない?」
「いえ、とても暖かいです。本当に、ありがとうございます」
「良いのよ。でも、その分うちの手伝いもたっぷりしてもらうわよ」
外への扉を開けると、冷凍庫よりも冷たい風が頬を叩いた。コートのお陰で体は芯まで温まったままだ。
日はすっかり昇り、空はプールの底と深い青色に変わっていた。雲一つ無い空と一年前のプールの風景が重なって、鼻を塩素の匂いが掠めたような気がした。

「さて彼女」
妙に芝居がかった口調だ。歩き方もまるでファッションショーのモデルのようだ。白い氷床と同じ色をした町並みがレフ板となって私達を照らしている。
先生はその先の台詞を続けた。
「ようこそ、ペンギンを祖先に持つ人類、南極人の街へ」


