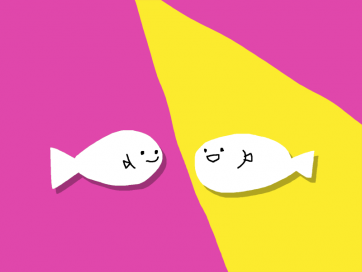トーキョーではずっと一人暮らしをしてるので、トーキョーのわたしはずっとひとりです。それまではずっと姉と同室だった。長いあいだ、二段ベッドの上に姉が、下にわたしが眠っていた。そのせいでいまではときどき幻姉がある。「げんし」と読みます。たとえば夜眠れなくて仰向けに携帯電話の画面を見つめながら、体勢を変える。すると携帯電話の画面の光は部屋の壁などを明るく照らしてしまう。わたしはとっさに「あ、姉を起こしちゃうな」とおもう。二段ベッドの上に眠る姉を起こしてしまう。けどほんものの姉ははるか神戸とか、旅行中だったらロシアとかスペインとかにいるので、起こしてしまうはずがなく、わたしの上空にいる眠る姉の気配は単にまぼろしなのでした。
このまぼろしを「幻姉」と呼ぶアイデアはトーキョーに来てから見た映画のひとつからもらいました。トーキョーにはいっぱい映画館がある。ひとりで映画を映画館に見に行くようになって、新宿や渋谷でも、映画館にだけは迷子にならず行けるようになった。「幻姉」はまだ迷子になるようなころに、渋谷の小さいアート系の映画館で見た、1989年のソ連映画です。監督はインガ・チシャーギナ、原題は「Орнитоптер」。これは日本語だと「はばたき機」なので、ぜんぜんまぼろしの姉ではなく、「幻姉」はかなりオリジナルな邦題です。オリジナルな邦題についてはものによっては思うところがあるのだけど、この映画に関してはなかなかお気に入りです。カルトムービーとして有名な作品なので、見たことはなくてもきいたことはある、あらすじは知っているというひとはけっこういるのではとおもう。
主人公は「じぶんには生まれなかった双子の姉がいる」、「その姉はじぶんといつでも一緒にいる」と子どものころから信じたまま大人になった女性です。たいへん夢見がちな人物として描かれ、その見た夢のとおりのように画面は展開する。「見えないけどずっと一緒にいる姉のため」と言って、主人公は常にじぶんのまわりに「すきま」を作っておく。だからどこにいても少し浮いているし、恋人ができても長続きしない。そもそも世間にも恋にも興味がなく、ただ姉と暮らすのが主人公の人生の楽しみなのだ。大学の構内に歩き回る架空のキリン、それにまたがる見えない姉。地下鉄に飛び交う架空の風船たち、それらを割らないように笑いながら避けて歩く姉と主人公。姉の姿はときどき、鏡に映る主人公自身の姿や、公園の鳥たちが飛び立って地面に作る偶然の影によって、予感のように表される。
「君の人生は君だけのものなんだから、そんな空想は捨てて、ほんとうの君らしく生きていくことだってできるのに」と元恋人に言われて、
「空想は生きてるうちにしかできないからね」と主人公が不敵に笑って答える場面がある。そこで主人公の声が、まるで双子が声をかぶせたようにダブって聞こえるのが格好良くて好きだった。この映画のなかでは、似た景色がオーバーラップするとか、近い言葉を重なるとかがシーンの切り替えの起点になることが多いのだけれど、この台詞は二重になってもどこにも続かなかった。
主人公の少女時代から、中年になって工場でうっかり(ほんとうにうっかり!)事故死するまでの一生が、メリーゴーランドのようにくるくると過ぎてゆく。そしてラストシーン、うっかりと死んでゆく主人公にカメラは近づき、カメラはそこで初めて主人公の視線の代わりをする。茶番のようにそこに姉は立っている。微笑んでいる。そしてわたしたち観客は、いままでのカメラがなんらかの客観ではなく、姉の視線だったことに気づく。だって、ずっと予感はあったのでした。この転換をうまく説明できなくてマジで悔しいのだけれど、うわー、わー、あの感動ったら。やばい。映画にあれほど感情移入したのは、いままででこの作品のあの瞬間だけだとおもいます。死んでゆく妹を見つめる姉の悲しみや、初めて姉の姿を見た妹の喜びとしてでなく、ずっと「姉」と同化していたのに、妹を見守っていたのに、突如としてそこから引き離され、もうわたしは(カメラは、観客は)姉ではない、誰も見守ることはあり得ない、という喪失感。
映画は朝9時20分からの初回を見ました。映画好きの友だちに、あの映画館で今度ソ連映画の特集をやるよ、と教えてもらい、調べると、先着順でポストカードプレゼントと書いてあったので、喜び勇んで7時前に行った。ほんとうは6時に着きたかったのだけど、迷子になって叶わなかった。ラブホ街をハラハラしながら歩いてやっと辿り着いた映画館はまだ開いておらず、並んでいるひともいなかった。宣伝用スチルの、映画にはないシーンを印刷したポストカードをもらい、結局わたしは他に5人ほどの観客とこの映画を見て、見終わるとふらふらになって部屋に帰った。大学は休んだ。映画で大学をサボるのは気分がいいと学んだため、わたしはこの先どんどん映画を見に行くようになる。どんどん迷子にならなくなります。
「幻姉」と、映画に似合わないおどろおどろしい書体で書かれたあのポストカードをいまはもう失くしてしまった。わたしはいまも一人暮らしをしており、こうやって存在しない映画のことを考えてはひとり楽しくなったりしている。少なくとも、生きてるうちにする空想は、生きてるうちにしかできない。
– – – – – – – – – – –
空頭(くうとう)病といへるかひこのやまひありあたまつめたく透きとほり死ぬ
/葛原妙子『朱霊―葛原妙子歌集』(白玉書房、1970年)
– – – – – – – – – – –
「罪と罰」の「罪」ならわかる 蝶が舌を伸ばす決意のことならわかる
/五島諭『緑の祠 (新鋭短歌シリーズ10)』(書肆侃侃房、2013年)
– – – – – – – – – – –