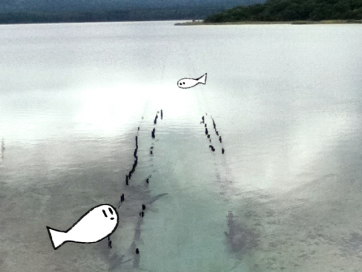– – – – – – – – – – –
◆おわび
連載の原稿を落としたため、代原として夢日記を掲載いたします。
– – – – – – – – – – –
2015年08月05日
海に近い家に引っ越す。砂浜に建つ白い四角い家。わたしたち姉妹はまだほんの子どもで、引っ越しの後片付けから逃走し、海で遊ぶ。浅瀬でぱちゃぱちゃやる。すぐそばをボロボロの魚が泳ぐ。はじめはボロボロではなかった。白い光みたいなのがいるとおもった。足元をすいすいとゆく白い光。捕まえようとするとボロボロの魚になった。ボロボロの魚はもう泳ぐ力なんて残っていないように見えた。わたしと妹は魚を挟み撃ちにして、捕まえる。魚を半分に割ると頭のある方が地獄に落ちていく。足元に広がった地獄には炎がごうごうと燃えていた。残った半分をお刺身にする。お刺身は家族の食卓で白く光っていた。窓の外では知らない子どもが犬を撫でている。子どもがうちに入りたがっているのがわかって、なんだか怖い。お刺身を食べてるわたしではないほうのわたしは玄関の二重扉の前に立って子どもと犬を静かに睨んでいる。
2015年08月10日
久しぶりの友だちに会うと結婚を頼まれておどろく。きくと友だちはすごく変わった病気に罹ってしまっていて、この国ではその病気の患者はすぐに処分される。なるはやで、お葬式の準備が必要だった。お葬式は必ず「家族」がおこなう決まりになっているのだけど、友だちは病気に罹ったことで実家から家族を解消されてしまったとのだいう。だから結婚によって誰かと家族を組まないといけない。未婚で、短い結婚歴を持ってしまってもかまわなそうな相手としてわたしが挙がったとのことだった。そういうことなら、とわたしは結婚を受け入れる。伝染する病気ではないのだし。
この国でも結婚は異性間の契約だったけれど、病気に罹った人間は性別が「病気」ということになる。だからわたしと友だちは同性だけど「異性」で、結婚が可能ということだった。「よろしくおねがいします」とわたしたちは頭を下げ合う。ついつい笑う。
結婚式はしなかった。わたしと友だちは短い同居を始める。わたしがひとりで暮らしていた古民家に友だちが転がり込むかたちだ。ままごとみたいに生活する。食器棚に食器が1セット増える。友だちの病気はだんだん進行する。病気にかかるとどんどんじぶんがわからなくなるものらしい。じぶんがわからなくなった友だちは、どんどん姿かたちを変える。魚になったり、マーガレットになったり、巨きなダチョウになったり。ときどき友だちはわたしと同じ姿にもなる。わたしたちは鏡のように向かいあって同じ声、口調で会話し、同じ笑い方をする。
「まださあ、チューもしたことないのに。結婚なんてね。そんでお葬式なんてね」と友だちが普段は出さない話題を出してふだんは言わない弱音を言うので、なんだいわたしはおまえのなかでそういうキャラなのかい、とおもしろくなる気持ちと、とても、とてもかなしい気持ちが一緒になって胃のあたりにあふれ、わたしのほうが泣いてしまう。
「もー、泣きたいのはこっちのほうだよ」って友だちはふさふさしたモップ猫に姿を変えながら、まだわたしの声と口調で喋る。
「知ってらい」とわたしは泣きながら答える。
お葬式の日はあっという間にやって来る。まだ友だちは生きているのにな。でも、決まりだから、ちゃんとお葬式をおこない、火葬し、遺灰をもれなく提出しなければならない。お葬式の朝、わたしたちの家ではお葬式会社の用意したパーティが開かれる。友だちの友人知人が多数出席する。友だちの元家族は来ない。友だちは爬虫類になって窓辺でぼんやりしている。知らない女の子が親しげに窓辺の爬虫類に話しかけているのを見る。数学の大会のテレビに一緒に出て、ライバルだったらしい。爬虫類はぼんやりしながらも、数学の話題にときどきうなずいていた。わたしにはさっぱり分からない話だった。同じ運動部にいたという集団が訪れ、パーティだからとみんな必死に笑ってくれている。友だちの友人知人たちが思い出話でわいわいしている横で、アネモネになった友だちは冷房の風に葉っぱを揺らしていた。アネモネの時間もあっという間に終わり、足の短い犬に変わる。もう何日も友だちの声をきいていなかった。
わたしはしゃがみ込んで、足の短い犬を持ち上げ、その鼻先にキスする。犬は人間みたいに目を丸くする。
「ほら、チューしてやった。口にしてほしかったら人間に戻れよ」とわたしは泣きながら命令する。犬に。ダメな喪主だなとおもう。
友だちはじつに久しぶりに友だちの姿となる。わたしたちが仲のいい友だち同士の子どもだったころの制服を着ている。少し若い、高校生の友だちを見上げて、とうとう身長を追い抜けなかったなと気づく。お互いがよぼよぼの年寄りになるころには追いつくというか同じくらいになるかもって考えたりもしていたのにな、とまた涙があふれる。そして、高校生にキスって犯罪かなっておもいながらチューする。影絵みたいになったふたりをみんな無視して、思い出話を続けてくれている。
ほどなくお葬式会社のひとがやって着て、お葬式の施設にわたしたちを案内する。ひとりでは歩けない友だちをわたしたちはえんやこらと運んでゆく。友だちは元の、人間の姿を保つことに必死なのだった。会場に着く。そこは映画館のような場所だ。3列に分かれて上手側の3箇所の入り口からぞろぞろ入る。わたしと友だちは列から抜け、オケピットみたいな一段低い最前でお葬式を見守る。壇上は花で飾られ、館内に天国かなってかんじの美しい音楽が流れ始める。すすり泣きがあちこちからきこえてくる。このあとは火葬だ、友だちは生きたまま焼かれることになるのか、とハラハラする。死ぬ用の薬があることをひそめた声で友だちが教えてくれる。
「死ぬなんて、やめよう」と大声を出したつもりだったけれど、夢によくあるとおり、こういう大事な場面で大声が出せない。
友だちはじぶんのお葬式を見つめたまま、返事をしてくれない。
「やめようって。遺灰なんて適当なものを提出しとけばいいし、顔が割れてるっていったって変身できるんだから、もう、残りの一生、木とかでいいよ。こっちが生きてる限りは世話してやるから。種とか、すごい小さいのになって、ここから脱出して。おねがいだから」
「そういうふうにできたら素敵だって、心底おもう」と言って、友だちは死ぬ用の薬を飲んでしまう。
平気そうにしているけど、わたしには友だちの恐怖がわかる。手足がどんどん冷たくなる。友だちはもう立てない。肩を貸す。友だちはもうきこえないし見えない。友だちの震える掌を持ち上げて、そこに「行ってらっしゃい」と指で書いた。「ふ」と友だちは息だけで笑った。うれしかった。友だちはわたしの掌を探り当てるとお返しになにかメッセージを残してくれるけど、友だちの指はもうガタガタだし、わたしは書かれたメッセージを解読することができない。できないけど「わかった」という。そういう他にない。さみしい。
友だちは死ぬとカラカラに乾いて、縮んで、赤ん坊のミイラのようになってしまった。ミイラを胸に抱いて、下手側の出口に向かう。1列になった元3列に続き、迷路のような地下を行く。途中で見つけた火葬場のひとにミイラを預ける。お葬式の行列はもうどこかに行ってしまった。火葬場をわたししか見つけなかった。これがほんとうに正しい火葬場なのか気がかりだけど、もうスイッチは押されて、どうしようもない。
2015年08月24日
誰かと電話をしている友だちに「住所を復唱するからそれをメモして」と頼まれる。
「漢字は書けないからねと」とことわりをし、全部ひらがなでメモしていく。
友だちの声に従って「おおあざ くらいもり」と書いたところで、「暗い森! すごい住所だねえ!」とつい友だちに呼びかけ、友だちは電話中なのだったと慌てて、友だちのほうを見ると、誰もいない。
– – – – – – – – – – –