「絵を描きたい気持ちがコロコロと丸まって、小さな犬コロみたいになって坐っている。」
これは日本の前衛美術家・赤瀬川原平によるあるエッセイ(※1)の書き出し。
いわく、この犬コロはふわふわして、トロンとして、とってもさわり心地がいいらしい。
同級生・荒川修作の大胆な絵の具の使い方の話から、光を獲得した印象派による喜びにあふれた筆触の話、デパートで催されていた展覧会での「タッチ不在」の絵について……
彼はこの手ざわりを手がかりに、絵画の”感触”を丹念になぞりつつ筆をすすめていく。
最初は犬コロの話していたのに、気づけば一緒にいくつかの展覧会をまわって、ついでに銀座の喫茶店でちょいとお茶まで楽しんじゃったようなほくほくした気持ちになったりして。
彼の周りをうろちょろしている犬コロは、読む私たちをここから遠くへ連れていくのがたいへんお得意のようだ。
森山安英個展「解体と再生」@北九州市立美術館
先日北九州市立美術館で見た森山安英の個展でもそんなことを思うことがあったので、今日はその話。
いやいやいや、いきなりその話て言われても、まず、森山さんて誰?とお思いのことと思う。
私も知らなかったし、wikipediaにも載っていなかった。
というわけで、まずは歴史的な背景についてざっとおさらいしておきましょう。
森山安英という画家は1950年代後半くらいから盛り上がったいわゆる”前衛”と呼ばれる一連の芸術の動きの中に位置付けられる北九州出身・在住の作家。
展覧会場にあった解説によると、冒頭に紹介した赤瀬川氏らによるハイレッド・センターやら、福岡で名を挙げた前衛美術グループ九州派やらよりも一足遅れて「集団蜘蛛」(1968-1973)として活動を開始。
後発だからこそ意識的に、よりラディカルで直接的なパフォーマンスを企み、仕掛けていったそうだ。
「ラディカルなパフォーマンス」とはたとえば街中で自分の排泄物を詰めたマッチ箱をお配りするだとか、天神のメインストリート・渡辺通りの交差点でセックスをやらかすだとか。
そんなむきだしのパフォーマンスの帰結として、1970年、デモ中に逮捕。
公然わいせつ罪・わいせつ図画公然陳列罪に問われ有罪判決を経て以来、15年にわたって沈黙する。
千円札を偽造した罪に問われた裁判を後にまるっとゲイジュツに落としこんでみせた赤瀬川氏と比べても、なかなか数奇な運命をたどっていらっしゃる。(※3)
「普通の絵を描く」という闘い
「ん?これ芸術?あっ、もしかして犯罪?あれっ?でも芸術????」というキワキワを東京の路上で攻めていた赤瀬川氏は、ハイ・レッド・センターの軌跡を振り返りこう話をしている。
“当時のハイ・レッド・センターがやり残したテーマに「やっぱり展」というのがあります。紐だとか梱包だとか洗濯バサミだとかまあいろいろやってみたけど、やっぱり風景画だよ、静物画だよ、人物画だよ、というんで、三人でそのオーソドックスな油絵を描いて、額縁入りの展覧会をやろうというものでした。(※2)
結局彼(ら)は、こうした展覧会を開くことはなかったようだけれど。
森山氏はというと、沈潜の15年を経て1987年に突如として絵画作品を発表するようになってから30年間、あくまで絵画というジャンルにこだわった闘いを続けた。
いったいどんな闘いだったか、というと。

これがまあなんというか、めちゃくちゃストイックで、はっきり言って、カッコいい。
チラシのメインビジュアルにもなっているこのシリーズは、1987年から発表されたアルミ顔料一色でマテリアル感全押しの「アルミナ頌」シリーズから数年後、少しずつ「色」とか「かたち」が画面に現れる時期の作品(《光ノ表面トシテノ銀色 17》1993年)。
以降、シリーズごとに素材の特性はより研究され、かたちはコントロールされ、企図された偶然が画面を構成していく。

《非在のオブジェ 11》1997年
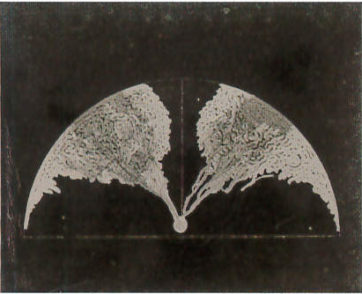
《レンズの彼岸 13》1999年
赤瀬川氏がそうであったように森山氏もまた2001年ごろから「普通の絵が描きたい」とぼやいていたそうだが、2002年以降の「光ノ遠近法ニヨル連作」シリーズなんかはほんとうにいい意味で、「普通の絵」が並んでいた。

《光ノ遠近法ニヨル連作 63》2008年
描きたい気持ちが大脱走
「うーん、かっこいいけど、ちょっと優等生すぎるかも?」
このまま洗練されて終わるのかと思いきや、2011年3月11日以降に制作されたシリーズを前にして、ぐらんと揺さぶられる。

《幸福の容器 04》2011年
「津波で打ち上げられた舟の映像をテレビで見たとき、”描かねば”と思わずにいられなかった」というこの作品は、あきらかにこれまでのシリーズとは様子がちがっていた。
画面下部から、始めも終わりもはっきりしない線が、ぼやー、ぺたーと這いつくばっている。
色の組み合わせも、今までほど厳格なルールがあるようには思えない。
まるで、これまで「普通の絵を描きたい」と強く思っていたご主人の手から、「描きたい」気持ちだけが急に駆け出しちゃったもんだから、今までしっかりリードを握りしめてきたご主人はびっくり仰天。
とまどいながらも、犬コロに必死に追いつこうと走り出している、ような。
そんな、主従が逆転した開放感がこの絵には広がっている。
その後の「窓」シリーズ、特に最後の石内都さんの写真作品を模写した2点ではもう、作家のコントロールはたしかな画力として絵を支える役に徹し、キャンバスの上にはふさふさした犬コロが走りまわっている。
絶筆と宣言された絵を前にしてはじめて、作品が観る人の手を引っ張ってたわむれる瞬間に立ち会ったような気がした。
—
ところで、展覧会や映画館やNetflixなんかで誰かがつくった作品と出会うとき、普段なら考えつきもしない考えや想像を思いがけず受け取ることがある。
ふいにいただいた贈り物を、なんとかあなたに別のかたちでお返しできたらこの上ないなあと思って、慣れない言葉なんぞ使ってみますね。
足元よれよれ、冷や汗かきかきで、ではまた来週。
※本文中の画像は全て北九州市立美術館パンフレットより引用。
※1:赤瀬川原平『芸術言論』「絵を描きたい気持ちの分析」より(岩波現代文庫、2006年)
※2:公判の記録は図録の巻末に記載されていて、これがけっこう面白い。まず被告人の冒頭意見陳述の題名が「権力に拮抗するDISCOVER JAPANまたは「観光」への誘い」ですよ。
※3:赤瀬川原平『東京ミキサー計画』p293(ちくま文庫、1994年)



