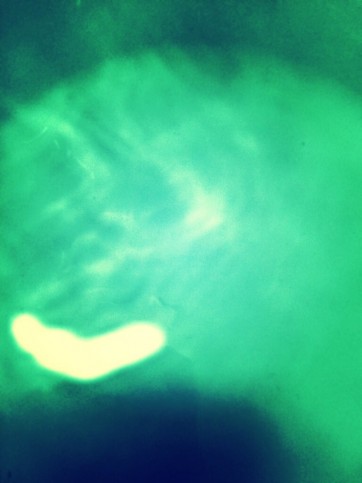「ももさんのうたを聴いていると、虫の音がよく聴こえるの。うたが聴こえる前よりも、虫たちのうたがよく聴こえる。電灯のひかりも、もっと眩しく見えるの。なんでだろう。不思議。」
歌い終えてタバコをふかす僕のとなりで、みきさんは静かにそうつぶやいた。10月下旬の井の頭公園。井の頭池のほとりの石畳に座りこんでいる。空は濃密な黒色に染まっている。秋風がときおり吹き、肌をふるわせる。肌寒いけれど心地よい静けさがある。東京にも時の流れを自然に感じることのできる場所があることをうれしく思う。星がいくつか輝いている。鴨や鯉やリスやカラスやコウモリが虫たちの静かな大合唱のなかで気ままに踊り遊んでいる。社会のなかにある見えない大きな歯車の音はここでは聴こえない。
僕は答える。
「そうだね。うん。知ってる。そうやってる。虫のうたがよく聴こえるようにうたうようにしてる。そうしないこともできるけど。でも、どうやっているかはよくわかんない。けど、そうやってはいる。そうしたいと思ってる。昔から不思議だったんだ。自然のなかでは、ほんとうにたくさんのいろんな生き物がいろんな声や音を鳴らしてるのに、不思議と自然の音楽はうるさくない。いろんな音が聴こえるのに、どれも自然に心地よく聴こえる。けど、人間が音楽を奏でると、自然のなかでは浮いちゃう。とたんにうるさくなる。まわりの音を殺してしまう。そうなりたくないと思ってる。そうならないようにしたいと思ってる。人間も、生き物のひとつだから、人間がほんとうに自然に音楽を奏でたりうたをうたったりすることができれば、虫や鳥や木や水や、そういうものたちとおなじように、自然のなかで、自然に響き、調和することができるんじゃないかと思ってる。自然の音楽を支配してしまうような暴力的な力ではなくて、そこにある自然にただ共鳴するようにうたえたら、って、ずっとそう、思ってる。自然は、聴かせようなんてつもりもないから。」
ライブハウスに通わなくなって久しい。20代前半はよく通っていた。自分にとっての音楽の自然を探しているうちに自然とそこから足が遠のいた。いまでもそういう場所が嫌いなわけではない。好きなところもある。好きなこともある。けれど、自分の音楽には、自分には、関係のないことや場所なのだということがいまではわかっているのだと思う。そこには音楽として境界を引かれた切り離された「音楽」しかないと僕には思えるから。そこでは、「音楽」しか聴こえない。僕が聴きたいのは境界を引かれてきれいに整えられた「音楽」ではなく、具体的な人間が、生きている時空間とともにその場とともに生み出す、そこでしか生まれない音楽。
三鷹に暮らすみきさんの街はかつて僕が住んでいた街でもある。その街に一軒の古本屋がある。古書 上々堂という名前の店だ。古本が好きな僕は、三鷹に住んでいた頃その店によく通った。その店のいりぐちのそばで毎週土曜日、夕方から夜にかけてビールをちびちびと呑みながらふらりとうたったりしていた。古本屋に暮らす一匹の虫のような気分でうたう僕がそこにいた。古本屋のお客さんのほとんどは僕のことを見ることなく本棚を眺めている。本棚を眺めながら、聴くとはなく聴いてくれていることがわかる。彼らはうたを聴きながら長居をするから欲しい本をたくさん見つけてくれる。古本屋も儲かる。帰りがけにみんな僕に投げ銭をくれる。いいうたをありがとうと声をかけて去っていく。たったそれだけの会話。それが僕はとても好きだった。そこにある関係が好きだった。演者と聴衆という二項対立の関係はそこにはなかった。僕はそこでただうたう。好きなときに好きなうたをうたう。古本屋のお客さんは古本を眺めたりうたを聴いたりのんびりしたりしている。おたがいに自由にその場所にいられる。それがいいと思っている。僕にとっての音楽は決められた時間に決められた演奏を再演するものではないから。ときには友達ともそこでうたった。お客さんともうたった。上々堂は僕にとって、三鷹の街中にある音楽の広場であり、古本屋という小劇場だった。三鷹のモモである僕はそこに住んでいた。そこにはただ、三鷹の街に暮らす人たちがいて、そこには古本と音楽と酒があった。そこにいるすべての人が音楽と古本のなかにいた。演者の前、ではなく。中。あいだ。そこには大きな違いがあるのだと僕は思っている。
浅草のアートスペースHATCHという場所で日替わりバーのマスターをしていた頃の僕もそんなふうにして音楽とともに遊んでいた。マスターである僕は、日本で一番多様なBGMが流れる店を作っていた。韓国アシッドフォーク、タイのファンク、インドネシアのクロンチョン、1940年代ヴェトナムにフランス音楽が流入したときに生まれたヴェトナムの新たな大衆音楽、台湾山岳民族の八部合音合唱、ジャズ、ヒップホップ、カントリーブルーズ…あらゆるジャンルと時代の音楽をかけながらお客さんに酒を振る舞いともにうたった。どこかでライブをするたびに共演者をスカウトして店のカウンターで気ままに演奏をしてもらった。二階のギャラリースペースでは友人たちがライブでもなんでもないセッションをしてひたすらうたい踊り遊んでいた。あそこも僕にとっての自由な音楽の広場だった。パフォーマンスではなかった。音楽のなかで遊ぶことだけがあった。
ときおりイベントをひらいては、Twitterで知り合った絵描きや映像作家や詩人などさまざまな作家を招き、その時空間をおのおのに自由に使ってもらい新たな表現を行う実験場として活用した。そこは音楽という表現ジャンルに限定されない、あらゆる藝術の有機的複合体としての生きられた時空間だった。おのおのの人間が、おのおののやりたいことをそこでやることができる場所。天真爛漫に遊ぶことのできる場所。そんな場所をつくろうと努力していた。そんな光景を眺めては、街中にその時だけ立ち現れる人間という生き物たちの祝祭を見るような気持ちになった。それは僕の好きな井の頭公園の虫や鳥や木や草や水の音やうたや踊りとおなじように、気ままで、自由で、自在な、そういう場所だった。都市空間と公園。僕はそこにおなじものをつくりだしたいと願っていた。人間がほんとうに人間であることができる場所。それは、自由自在な自然の時空間とおなじものなのではないかと僕は考えていた。そしていまもその想いは変わらない。人間がほんとうに人間であるための場所。僕がつくりたいと願うのはそういう場所だ。西田幾多郎の「場所」、折口信夫の「産霊」は僕にとってそれらをまなざすものであり、僕はそれらをこの世に具体的にかたちづくろうとして東京の地にいた。
「人間が、自分を、他者を、殺さずに、このまちで暮らすために、なにができるだろうか」
西暦2007年、19歳の僕が立てたひとつの問い。僕の中には、いまもこの問いが荘厳なしずけさをたたえる焰のように燃えている。人間がほんとうに人間であることは、人間が、自分を、他者を、殺さずにこのまちで暮らすことにほかならないと僕は信じている。そのためにできることは、山ほどある。星の数ほどある。やりつくすことはできずにおそらく僕はそのうち死ぬ。それでもいいと思っている。願いは無尽だ。それは祈りだ。叶えるために祈るのではない。祈りは祈りそのものとして息づいている。
あの夜がいつのことだったかはもう忘れた。けれど、あの夜に見た光景を僕はいまだに忘れられずにいる。
Taylor DeupreeのNagative Snowという曲を聴きながら三鷹の街を歩き家路についていた僕は、目の前に突然、黒いモヤが立ち込めるのを見た。その黒いモヤは次第に濃密になり、やがて漆黒の宇宙空間そのものとなった。僕は歩いている。三鷹の閑静な住宅街。僕の足はしっかりと路面を踏みしめ、目はその路上を眺めてもいる。しかし、その目は同時に目の前に広がる黒々とした宇宙をも眺めている。路上と宇宙。ふたつの時空間はそこに同時にあった。僕はただそれらを眺めた。すると、宇宙空間の下方がゆっくりと陥没し、そこからエメラルドグリーンに輝く光が揺らめき出してきた。その光はアラスカの天空にたなびくオーロラのような神秘的な光。それらが次第に数を増し、気づくとその光の束は、エメラルドグリーンの光に輝く地球をつくりだしていた。僕は歩きながら、その惑星の美しさに魅入った。あの美しさを言葉にすることは僕にはできない。ただ、いままで見たもののなかで最も美しいもののひとつであったことは確かだ。
僕はエメラルドグリーンの地球を見つめていた。地球は光の帯を引きながらゆっくりと廻っていた。そのとき僕は、はじめてこのかたちの僕がいま生きている、この惑星のほんとうのすがたを見たと思った。地球は青かったとかつてアームストロング船長は言っていたが、僕にとっての地球はエメラルドグリーンだった。そして、それはまぎれもなく、光だった。
井の頭池のほとりのベンチに腰かけて、わかこさんは静かにほほえんでいた。風はもうやんでいた。三日月が井の頭池に映り、ゆらいでいた。それはクラゲのように見えた。月が沈んでいくとともにクラゲも消えた。クラゲは井の頭池に沈んでいった。そこは海ではなく池だけど、海の月であるクラゲは水に還っていった。黒々とした空に染められた緑色の樹々は井の頭池に鏡写しとなっていた。地上と湖面はその境界線を境に互いを鏡のように映していた。
黄色と青色を混ぜることではじめて緑色が染まるというはなしを草木染めの志村ふくみさんの本で読んだことがある。光の黄色と、闇の青。このふたつがなければ、自然の色である緑の世界のひかりは灯らない。緑は地球の晴れ着なのだと思う。
僕は今日、東京から岐阜へ帰ってきた。ここにも緑がある。東京よりはるかに多くの緑色の自然の風景がここにはある。この自然のように在れたら。そのようにうたえたら。そう願う。それが僕にとってのほんとうに人間であることのひとつのことであるから。緑色の自然と調和することで、僕は僕を消し去り、僕は自然の一部となる。うたっているあいだ。その時間のなかで。僕は自然になる。僕にとってのそれは、誰かにとっては音楽ではないだろう。それでいい。おのおのの自然の営みのなかで、おのおのの自然と調和し、おのおのの自然に還る時間。そこはひとつの、ほんとうに人間である時間。そして、僕はそれを音楽という名前で呼んでいる。そんなふうにして、おのおのの人間が、おのおのの自然のなかで、おのおのの自然な営みとともにひとつの時空間をわかちあうことができたなら。僕はそんな場所を想像する。それは都市でも田舎でも可能な場所だと思う。おのおのの人間が、おのおのの人間を生かし、生かし合う場所。それは自然のなかに生きるあらゆる存在の静かな音楽となり、緑色の惑星のうえで行われる祝祭となる。呪いと祈りを調和させて、かつて、そして、未来に向けた生命の祝祭。そんな場所と時間のなかで、あらゆるものたちと呼応しながら、その場限りのうたをうたえたら。そんな未来を懐かしく想像する。いつまでも。
「時間。それは、いつもひびいているから、人間がとりたてて聞きもしない音楽。でも、わたしは時々聞いていたような気がする。とっても静かな音楽。」
『モモ 時間どろぼうと ぬすまれた時間を人間にとりかえしてくれた女の子のふしぎな物語』ミヒャエル・エンデ作