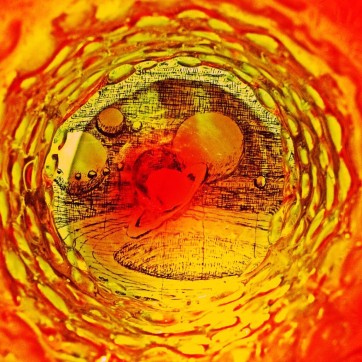無数の電線にその身を縛りつけられて
電信柱は 今日も明日も昨日も
そこに立っている
おそらくそれは
立ち続けるのだろう
その身が 何かに
壊されるまで
おそらくそれは
立ち続けるのだろう
無数の家々の電燈に
明滅するいのちの光に似せた
闇夜を隠すための
それから逃げるための
無数の人工電燈を灯すために
おそらくそれは
立ち続けるのだろう
そして
いつの日か
その役目を終えたとき
その身を壊されるのだろう
もう おまえは要らないと
見知らぬ誰かがそう決めて
おまえのその身は滅ぶだろう
そうだとすれば
電信柱 おまえは
なんのためにそこに立っているのか
なんのために
その身に無数の電線を巻きつけて
身動き一つとることなく
雨風の中
一つの文句を言うこともなく
おまえは立ち続けるというのか
おまえの文句を
おまえの愚痴を
聴かせておくれ聴こえぬ声で
頼りないこの耳に
おまえの声を聴かせておくれ
電信柱
おまえは
無数の家々に暮らす無数の人間の
無数の暮らしの中に無数の光を灯して
そして
いつの日にか 消えるという
そんなことが
おまえの望みか
電信柱
おまえに意思があるのなら
聴かせておくれ
電信柱
おまえの声や言葉たち
それはこの世のそれとは違くても
俺はおまえのうたを聴く
聴かせておくれ
電信柱
世のためにその身を消尽した
イエスキリストのようなおまえの身を
俺は見て
おまえの声なき声を聴いて
俺は
どうしたらいいのか
考える
俺は
どうしたらいいのか
俺には
何ができるのか
俺は
考える
おまえが
それを望むなら
おまえに
うたがあるのなら
俺はすべてで
それを聴く
聴かせておくれ
電信柱
人々のために磔にされた
立ち続けるおまえの身
捧げられるべきものなど
ほんとうははじめから
ないんじゃないのか
そのものとしての運命と
そのものとしての意志と
その葛藤のなか
その対立の
狭間のなかで
人々の暮らすこの街を
照らしつづけて
いつか死ぬおまえよ
俺は
おまえに生かされている
そして
だから
謝りたいと思う
おまえが立ち続けることなしには
俺たちは
俺たちの生活を普通に営むことさえ
できないのだ
そんなふうにして俺たちは
おまえをこの街に独り立たせ続けている
そのことに屁でもないという顔をすることは
俺にはどうもうまくできないのだ
おまえは俺たちのために立っている
俺たちは俺たちのためにおまえを立てた
だからおまえは立ち続ける
おまえはそのためにうまれた
だからおまえは立ち続ける
でも
それは ほんとうか?
おまえは ほんとうに
それを望んだか?
おまえは ほんとうに
そうしてうまれたいと
それを望んだか?
おまえは
おまえのかたちを
ほんとうにそれを
望んだか?
俺の前に立つおまえよ
おまえいつも俺の前にいる
だからおまえをお前と俺は呼ぶ
だが おまえよ
おまえのかたちを
おまえのすがたを
おまえのなまえを
おまえのお前で
俺は
いつも
言葉にできない
訝しさのようなものを
感じるんだ
おまえは
おまえでなくとも
よかったのではないか
そう問う俺がここにいる
俺たちのためにうまれたおまえは
俺たちのためにそのかたちを全うして
やがて俺たちのなかの誰かの手によって壊されるのだ
それが俺は
なんだかすこし
おかしいと
そう思うのだ
だっておまえは
おまえでしかなく
電信柱という名前から
いつだってこぼれ落ちる
たった一つの
おまえなのだから
俺の前にいる
おまえであるかぎり
おまえにおまえの代わりはないのだと
俺はそう思うのだ
だからおまえよ
聴かせておくれ
おまえの声で
おまえの言葉で
おまえのうたを
聴かせるものかと思っても
俺はかならずおまえを聴く
俺は飽きずにおまえを聴く
おまえを聴くことをやめない
それが俺だ
俺は聴き続ける
電信柱であるおまえや
それ以外の無数の名前を
人間たちによって付けられた無数のおまえたちのうたを
理由など ない
俺は
俺が聴きたいから
そうするのだ
おまえがたとえうたわずとも
おまえが沈黙のなかに顔を埋めようとも
俺はおまえのすべてを聴く
俺が俺であることは
俺がそれを聴くことだから
俺はいつまでも永遠におまえたちを聴く
そして俺は うたう
いつまでも うたう
声が枯れても うたう
のどが潰れても うたう
この身が滅んでも うたう
うたいつづける
俺が俺でなくなっても
俺がこのかたちをやめても
俺が人間をやめても
俺が俺を忘れても
俺は俺を うたう
俺が俺をうたうことは
俺がおまえを聴くことだ
おまえのうたを聴くことが
俺がおまえをうたうこと
俺がおまえをうたうことが
俺が俺をうたうこと
そのときおまえは うたうのだ
俺がおまえを聴くときに
おまえは知らずにうたうのだ
おまえの知らないおまえのうたを
だから俺は 聴いている
うたわなくても 聴いている
口がなくても 聴いている
耳がなくても 聴いている
息をしなくても 聴いている
ここに俺がいるからだ
俺のからだがあるからだ
俺のこころがあるからだ
俺を俺にし続ける
たましいというものがあるからだ
だから うたえ
おまえよ
風前の灯火にあるおまえよ
どうせ死ぬなら
死ぬまでうたえ
おまえが死ぬまで俺が聴く
だから うたえ
おまえよ
生きていることが辛いとか
涙を流して死を望むなら
うたえ うたえ うたえ
死ぬことなんて
たぶんたいしたことじゃない
たぶん素敵なことじゃない
たぶん楽しいことじゃない
生きてることと
おんなじだ
俺やおまえが
いま ここに
このかたちをしていることと
おんなじだ
いつか そこで
このかたちをやめることと
いま ここに
このかたちをしていることと
それはべつに
おんなじだ
おまえは電信柱だし
俺は人間だ
おまえは俺の前にいる唯一無二の電信柱で
俺はおまえの前にいる唯一無二の百瀬雄太だ
だから俺らはそれでいい
唯一無二の百瀬雄太と
唯一無二の電信柱
ここで俺とおまえと
ふたつで間違いない
だからそれでいい
その名前を剥ぎ取っちまえば
そこにあるのは
ただの俺とおまえだ
そして
俺とおまえなんて言葉さえ
剥ぎ取っちまえば
そこにあるのは
もう なんだ
もう ひとつだ
俺もいないし
おまえもいない
それでも
俺もいるし
おまえもいる
だから
それでいいじゃねえか
笑えよ
うたえよ
誰かのためなんかじゃねえ
誰かのためになんて
そんなものは
糞食らえ
おまえのために うたえ
そして 笑え
そして 泣け
おまえがおまえであることを
俺に聴かせろ
そうでなければ
おまえは
一体
なんだというのか
誤魔化すんじゃねえ
綺麗なおまえなんて見たくもねえし
反吐が出る
そんなおまえには
犬の小便がお似合いだ
汚ねえまんまで うたえ
見るも無残に うたえ
バカ丸出しで うたえ
泣け 叫べ 祈れ 穿て
突き抜けろ
その先に
見ろ
聴け
ふれろ
感じろ
味わえ
嗅げ
想え
呪え
そして
黙って
そして
うたえ
突き抜ければ
ほら
無限の青
無数の星たちが明滅する
無限の空
ちっぽけなこの街に暮らす
ちっぽけな俺たち
おまえも含めた
すべての俺たち
いま ここで
無限の宇宙の
ど真ん中だ
どこまでもちっぽけな俺たちは
どこまでもでっかいこの宇宙の
いつもその真ん中だ
俺たちが俺たちであるかぎり
それがそれであるかぎり
名づけられないものが
そこにある
意味なんてあってもなくてもいい
勝手に読め
見えない文字を読め
書かれていない言葉を読め
聴こえない音を聴け
触れないものに触れ
匂わないものを嗅げ
味のないものを味わえ
おまえには
おまえのからだがあるだろう
だからおまえには
それができる
いま できる
ここで できる
だからからだがあるんだろうが
忘れるんじゃない
思い出せ
知っている
——————–これ———–は————境
——–界線———-で——-あり—————————-それゆ———-え—————僕は——————–この———-連載———にて—————–この————線————を———–よ—く———-使った——————お気づき——–だ——–ろ————-う———-か———————————————————————————これ—————は——————————————線—————-でもあるが—————–点—————–でも———-あり、———————これは————-点———————の————-連な—-り——–で———————もあるからして————-これら—————————-は—————-点線——————–であり————–点線である、———そのこと———-は、————-実は———–本来—————-そうである———というこ——————-と、————-でも、————あり、——————–線————–とは、————–点、———–即ち、———–[・]—————-や—[、]—————、———でもある、———–ということであり、——–点——–で———あ———–るこ———–とは、————-線であ——–ることで—–も———-あ—–るのであり、————線———-と————–点——–とは—————-とも————–に——–ある————-ことであり、—————-もの、———であり、———-そう、————-見えるか、見えないか———どちらに見える—————か————と————————————-いうことでもあり、—————–それは、——–だから、——–同時———-でも————あ——–る——-の—-だ、———-と、——-ここに、———点と————線と———-その————-文字を———————-知覚———–し————–そう———————それを納得———-したり——————————疑った——–りする————-あなた———-は、——–いま、———————————————————————————————————————————-
何を見ていますか?
文字を見ていますか?
文を見ていますか?
なぜこれは文ですか?
なぜあなたはこれを読めますか?
どうやってこれを 見ていますか?
ここにあるのは ほんとうに文字で
ほんとうに 文 ですか? ほんとうに
そうでしょうか?
疑ったことはありますか?
それ が それ
で あることを
では、よく見てみましょうか。
iPhoneの画面でこれを読んでいる方はiPhoneの画面でかまいません。PCの方はそのままPCでかまいません。よく見てみましょうか。
あなたの目に映るのは僕の書いた文章です。それは間違いのないことです。僕はこの文章を書きました。それはいまのあなたの時間では過去形ですが僕はいまこの文章を書いています。書いているといまここに書いているのですからそれはそっくりそのまま事実です。でも僕は文章を書いているのでしょうか。ほんとうに、文章を書いているのでしょうか。どうでしょうか。
–
いまこの文の上にあるのは、点です。
おそらく、点です。
しかし、点とはなにか、僕はよく知りません。
ここに書いている文章は文によって構成されています。文は文字によって構成されています。組織されているといってもいいかと思います。僕はここに文字を並べることで文を書き、文章を書いてきました。それを僕は第1話で言の葉の散歩をするとそう書きました。だいぶ遠くまで歩いてきました。自由に書いてきました。毎話なにを書くのかわからぬままに書いてきました。そしていまここに辿り着きました。そうやって文章を書き連ねてきました。
が、どうでしょう。
あなたがいま読んでいるこの文章の表示されている画面に映っているものは、おそらく、ほんとうは、点、です。
それは目では見ることのできないほどにちいさな点で、目には見えないちいさな点が寄り集まって点灯することによってそこに文字が浮かび上がります。それがこれらデジタル機器の画面の仕組みです。そこには極小の光の点があるだけです。だからここには点があるだけで、文章も文も文字も、ない、とも言えます。あるのは、点、ですから。
そして、点、は、無数に寄り集まりながら、線、を描きます。だからここに文字があります。文字という文字を読むことができるのは文字という文字を組織する極小の点の集合体がここに明滅することができるようになっているからです。その精度がとても高いので僕たちはその文字という文字を知っていればそれを文字と読むことになんの疑いを持つこともせずそれを読むことができます。便利ですね。
でも、忘れないでいてほしい、というか、僕が個人的には忘れたくないことは、あくまでそれらは、点、でもあるということです。
これは、画面の話ですが、それに限らないもっと大きな話です。それこそ、宇宙とおなじ大きさの話です。
点と宇宙は同じものでもある
おそらく僕はそういうふうに
点と宇宙を見ています
だから
僕は
線が嫌いです
線は
嘘つきだから
でも
嘘つきだから
線は
いろいろなものを
産み出すことができます
それは線の持つ
力 かと思います
この連載を通して僕は、いろいろな境界線上を歩いてきた。文字という線を書き連ねながらそうして僕は書いてきた。そしていまここまで来た。ここまで来たとは言っても、それは間違いではないけれど、ここまでというとき、それはどことどのように比べて、ここまで、なのか。それは第1話からとも言えるけれど、それをそこと呼ぶことは、間違いではないけど変なことだと…ブツンッ………
—————————————————————–
この上の文章を書いているときの俺はどうもうるさいしウザいので俺はこの僕をここで遮断することにいま決めた。その受信機をいま切った。通信は途絶えた。僕はそこで中途半端に終わった。だから僕はもういない。
—————————————————————–
ネロは 今日も境界線上を歩いている それはネロがそこを歩くことを望んだからや ネロは今日も歩く そこには線がある その上を選んで歩く ネロは線のことが好きで嫌いだ だからネロは線の上を歩く
境界線上を歩くネロのふたつの目は その境界線によって分け隔たれたものが見える ネロの真ん前には 誰かが引いた線がある それはいろいろな線 ひょっとすると 僕が引いた線もそこにはあるかもしれない 人は線を引く そういう生き物だから そこにはいつも線があるし 猫だけど犬で 犬だけど人である僕は ネロとしてそこを歩いて その線を引いたり見つめたり眺めたり いろんな仕方でその上を歩いている
そこに線はある だからネロはその上を歩く けれど ネロがその線の上を歩くと その線は彼の歩いたあとから消えてゆく ネロが歩いたあとには そこに引かれていた線は消えていく ネロはそういう歩き方をする 僕はそう思っている 僕であるネロはそうして境界線上をゆく だから そこでは 線はあることとないことと同時なのだと思う そこに線はある けれど そこに線はない 僕はネロだけど ネロはネロだから ネロは僕じゃないけど ネロは僕だ そう思っている そう思って僕は 第1話に 境界線上のネロという名前をつけたことばたちを書いた のだと思う おそらく いまになっては そう思う
—————————————————————–

10数年前に行った沖縄でオカンに土産として買ってきた琉球ガラスのコップをいまも使っている。コップは上から下に向けて赤から黄色のグラデーションを描いている。コップの表面は月のクレーターのようにぼこぼこと隆起していて、僕はそのぼこぼこが不細工だからとても好きで、そのコップを陽の光に照らしてみた。いま暮らすこの家の周りには、こないだまで住んでいた家の周りにたくさんいた木や草や虫たちの気配があまりしない。朝、窓を開けると、遠方には山。すこしだけ遠のいた山の風景と、国道を絶え間なく走り続ける人の車たちの音が聴こえる。車が走り抜ける音が聴こえるたびに、そこに人がいることを感じる。人が走っている。車に乗って。どこかへ向かう。帰るのかもしれない。この窓に国道という線は平行だから、車たちはこの部屋に交わることなく左から右へ右から左へと走り去っていく。でも、そこには人がいる。おそらく人がいる。だから車が走っている。たましいと呼ばれるものが右往左往している。人はいつも右往左往して生きてゆく。いずれかの線の上。それを道と呼ぶ。その線は誰かが作ったもの。車で走るその場所はそうだ。誰かが作った道。誰かが拵えた地上の線。そこをゆく。走ってゆく。それでもいい。それが車の走り方だから。火を灯し、オイルを燃やして彼らはこの道を今日もゆく。その音を聴きながら僕は琉球ガラスのコップを貫く光を眺める。太陽の光を透過して、琉球ガラスは火の鳥の尾っぽを僕に見せてくれた。火の鳥。不死鳥。中学のときに描いた。美術の時間にそれを描いた。自分を表現するものを描きなさいという課題にたいして僕はなぜか火の鳥を描いた。月のクレーターのようにぼこぼこと隆起する茶色の大地がある。そこには草も木も生えていない。死んだ大地。その大地の上空を不死鳥は飛ぶ。そんな絵だ。水彩絵の具を水に溶かして何度も何度も色を重ねた。こまやかに燃えるすべての火の粉を描き込もうとしていた。火の子供達。それらのすべてが生きるようにして丹念にそれを描いた。そして火の鳥はそこに生まれた。僕の火の鳥。僕は火の鳥。そう思って描いた。15歳の僕。あの絵はいまもひとつの故郷のようなものなのかもしれない。そう思いながら僕は琉球ガラスを見つめ、このコップを透過した光に浮かぶ赤く燃えたつ火の鳥の尾っぽを見つめている。
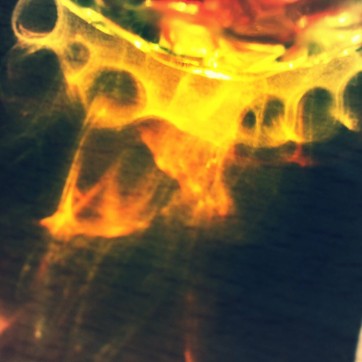
水のようにあれたらとおもう。水のようにあれたら。水はあらそわない。水はあらがわない。水はおそれない。水はとまらない。水はうたがわない。水であることを全うする。それはどこでもゆける。
河という蛇行する自然の線猫を描きながら河の水は海へと向けてひた走る。数多の河が地上にある。それらはいずれも河である。どの河がえらいとかはない。どの河も河に違いない。
それらはやがて海へとたどり着く。海。ひとつのもの。ひとつの場所。生き物たちがやってきた場所。やがて還る場所。そこへ向かってすべての河は流れてゆく。河であることをうたがわず、河であることにあらがわず、河をやめたいなどと思うこともなく、河は河として、そのなかに、無限の水の粒子たち、太陽の光をきらきらと反射しながら流れてゆく。無限に蠢きながら形を変えて、それでも水は水として、その河の線、その河の道に従いながら、水は水を全うする。
海になったかれらはやがて蒸発して空へと還り、水蒸気となって空を漂う。あの虹色のクラゲたちのように、ゆらめきながら虹を描く。空に描かれる虹は僕たちの目には見えない無数の水の粒子たち。それらのからだに映る光が、僕たちの目に映るこの空に虹の半孤を描きだす。望むことなく選ぶことなく描きだす。空白のキャンバスにいつもそれは描かれる。
それらはやがて雲となり、ここやそこや彼方へと、風に吹かれて流れ去り、その地に雨を降らすのだ。恵の雨。枯れ果てた砂漠にもやがて雨がふるだろう。慈悲の雨。放浪の民はなにを想うか。天から降りそそぐその雨水を渇いたのどの奥へと流し込み、その唇を潤し、僕たちのからだは今日も水でできている。水のようにあれたら。このからだのなかを流れる水のように。それは音楽に似ていると思うんだ。そして、あの日死んだコロにも似てると思うんだ。
どんなとこだって行けるんよ どんなとこ 行きたいとこならどこだって いつにだって行けるんよ だって俺らは 生きてるし 死んでるし 人間やし 犬やし 猫やから ネロ 音の路て書いてネロや お前も俺もあいつもそこのあんたも みいんな ネロやで
———————————————
そう。僕たちはどこへだって行ける。僕たちは歩いて行ける。どこへだって。それをあなたがほんとうに望むなら。
———————————————
音の路地裏でまあるくなってるコロ お前も一緒に行くか? 連れてったるわ そんなとこおってもつまらんやろ な だから行くで 音楽は無限や 形もないし 時間もない どこへだって行ける どんなとこへも飛んでいける あんたの耳のなかだって 星の果てへだってな
————————————
真っ黒な宇宙にひとつぽつりと浮かんでいたあの部屋。僕はもうそこにはいない。
そこにあなたはいるか。だったらいっしょに外へ出よう。外にはあなたの部屋にはない景色が広がっている。その狭い路地裏にはないものがここにはある。そこには空がある。そこには星がある。そこには色々な色をした色々なものがある。生きているものがある。死んでいるものがある。僕の目の前でカマキリが車に轢かれて死んだ。それもある。山の木々からどんぐりが落ちてきて坂道を転がる。それもある。たんぽぽの綿毛がふわりと空を飛んでいる。それもある。色々なものがある。鳥が鳴いている。青い空。
空のからだは鳥
鳥のたましいは空
————–
みいんなのなかのネロ 好きなとこへ歩いていけるとええなぁ
俺 恥ずかしいけど ほんまに思ってるで ほんまにそれがいい だって 生きてるんやもん 好きにしたらええやん なんであかんの 誰があかんて言うたの そんなん誰も知らんやん 言われたふりしてるだけやで
————–
自由とはみずからをよしとすることだとあの人が言っていた。そうだよ。そこにあるそのあなたやわたし。自分。みずから、おのずから、分かたれたものたち。あらゆるそういうものたちが、みずからをよしとし、みずからとして在ることのうちに、自由自在がある。自由は、なにかからの、どこかからの自由というものじゃない。どこにいても、それはある。あるというのはすこしちがう。あなたやわたしが、自分をそのままに、まるごとに、それをよしとして受け容れるとき、そこにはもう、自由がある。その瞬間に、ある。だから、自然は、自然なんだ。みずからがそうあることをそのままにまるごとに、そうあるだけだから。
——
武蔵 あのな
実は最近 声を聞いた
……誰の?
……
声って……
誰の?
それによると
わしの
お前の
生きる道は
これまでも
これから先も
天によって
完璧に決まっていて
それが故に
完全に自由だ
根っこのところを
天に預けている
限りは
『バガボンド』29巻 井上雄彦
沢庵和尚の言葉から一部引用
—-

根の国。天上と地上と地中。分かたれていながらそれらはつながっていた。第3話にそれを書いた。
黒い部屋にいるあなた。そこは白い部屋にもつながっている。そこは青い部屋にもつながっている。そして、それはエメラルドグリーンの惑星にある。その惑星はわたしたちのなかにある。
赤色の血を右腕から流す人らしきものが染める青い海の底には深海の黒色。虹色に光り輝くクラゲたち。深海の鏡でありシャーマンであるクラゲたちを潜り抜けた先、深海の底には、海の根っこには、無限の星空がある。そこで、海と空とは一つであり、天と地は上下を逆転させながら連なり、一なる無限の円環。そこに無限の星空の光を明滅させる無限の宇宙がある。
黒い部屋。そこはおそろしいところだけれど、その色は、宇宙の色にもつながっている。その部屋は、あなたのなかにある部屋だけど、そこにあなたは住んでいて、その外には出られないと思いこんでいたとしても、そこは、宇宙につながっている。どれほど孤独な暗闇も、見つめていると、宇宙につながっている。だからそこは、無限の宇宙の一点でしかないちっぽけな部屋であり、同時にそこには、無限の宇宙がひろがっている。そして、光が灯る。明滅する無限の星空に見える灯。あまねく惑星、銀河がそこにある。
だから、どこでもいける。根っこを天に預けているあなたなら。そこはどこでもあるどこかだ。そして、ここは、ここであると同時に、どこでもあるどこかであり、いつでも、いつかのいつかなのだ。そう思う。そう思うことから、時が、場が、動きはじめる。内臓の蠢きのように、光が、粒子として、波として、放射される。どこまでもゆける光のように。それは重力にも似て。重力もまた、どこへでもゆけるから。万有引力は差別をしない。それは境界線を引かない。それが引くもの、そこにある引力は、見えない糸、それは、どんなにちいさなものにも働き、引き寄せる。孤独の発明。われわれがわれわれであることはわたしがわたしであることと同時にあるのだと、それが教えてくれる。重力がなければ、このかたちを、保つことさえ、できないのだから。だから、痛みはつねに、恩寵とともにある。
どんな部屋にも行けるよ。この空の、この海の、その間に引かれた一本の水平線。その境界線が引く空海には、あらゆる色があるから、あなたがそれを見るならば、どんな部屋も、あらゆる部屋につながっている。いま、ここから、すこし離れた場所へゆける。それをあなたが望むなら。
人のまんなかには、種のようなものがあるんだと思う。それは人に限らない。あらゆるものたちがおのおのであることのまんなかには、種のようなものがあると思う。それはドングリにも似てる。僕の左手が拾いあげたドングリ。ここには、意志が宿っている。
ドングリがドングリとして地上に産み落とされることは、その木が、生命を繋いでゆこうと意志することだと思う。そこには意志がある。たとえ思考や意識や意思がなくても。考える必要はないのだと思う。考えるまでもなく、悩むまでもなく、意志はそこにただ宿っているのだと思う。
目には見えない種がある。そこにも。ここにも。あそこにも。僕のなかにも。あなたのなかにも。それはかならず、宿っている。だからあなたは、おかあさんのおなかのなかから、産まれてきたのだと、そう思う。
その種は、いつでも待っている。いつまでも待っている。産み落とされたその場所で、雨が降ることを、風が吹くことを、太陽が巡ることを、夜が来ることを、大地に在ることを、鐘の音が鳴ることを、火が燃えることを、灯が灯ることを。太陽と月とが廻り続けることを。いつでも、待っているのだと思う。
そういう種を、意志と呼ぼう。僕はそう呼んでいる。根っこを天に預けて。それは天上と呼ばれるところでもあり、この地上、この大地の下でもあるところでもある、そういうところ。天上天下。そこに境界線はない。そこにあるのは無限の円環。だから、根っこのところを天に預けていることは、地中深くに、暗い暗い闇夜にも似た大地の底に、根をはることと、同じことなのだと思う。
そこに種がある。そこはここでもありどこでもないここ。それはどこかであり、あなたのまんなか。そして、あなたのまんなかは、わたしのまんなか。そういうところに、種があり、意志がある。
おのおのの意志。
それだけでは、意志は芽を出すことはできない。意志だけでは、産まれることはできない。生きることはできない。
だから、別の、異なる意志を持つものたちが、この世界には、ともに生きている。
空の雲たちが雨を運んでくれる。
雨がふり、水を恵んでくれる。
太陽の光や土の中のものたちが、
養分を与えてくれる。
種を運ぶ鳥がいる。
土を耕すミミズがいる。
数え切れないほどの生き物たちがいる。
そして、数え切れない生き物たちがやがて死に、土に還り、風になる。
骸に流された涙もやがて悦びに変わる。
独りではないのだ。
どんなものでも。
独りではない。
生かされている。
死にゆきながら、
つくられている。
だから、
死ぬなんて、
言うなよ。
死にたいと思うくらいなら、
死ぬことすら許されていないと思うなら、
すべて忘れて、
旅に出ろ。
そこにある無限のものたちを見るんだ。
そこにある無限の音楽を聴くんだ。
そこにある無限の生命の劇場で、
それぞれのものたちの、
それぞれしか知りようもない、
無限の、
ほんとうに無限の、
生命の劇を見るんだ。
そして、
彼らとともに踊ればいい。
真善美など糞食らえと笑えばいい。
誰かに言われたことなど、
知ったことかと笑えばいい。
傷だらけになることもある。
血を流すこともある。
そうしたら、
その血を、
あの透明な液体に流して、
再び、初めから、
おまえの海をつくりなおし、
おまえの海に還ればいい。
そうして、もう一度はじめから、
あたらしく生まれ返せばいい。
死ななくても、生き返せるんだ。
だから別に死ぬ必要はない。
そんなふうに思う必要はない。
そんなふうに思うのは、
忘れているからだよ。
こどものときにいた、
あの場所を。
だから、
忘れたら、
もう一度、
何度でも、
帰ろう。
そして、
そこで、
ともに笑おう。
やさしく眠ろう。
静かに眠ろう。
いつかまたその場所で。
そこに俺はいる。
そしてあなたもいる。
みいんな、
そこに、
いる。
独りではない。
根っこを天に預けているうちは。
だから望め。
ほんとうの意志を生きるのだと。
そこにある種のうたを聴け。
生きることがうただと知るんだ。
あなたはもう知っているから、
思い出せ。
それだけのことだ。
なにも難しいことじゃない。
たかが生き物じゃないか。
息をしているだけ。
飯を食って、ウンコをして、
寝て、セックスして、遊んで、
生きて、死ぬ。
生き物なんだから、そうだろう。
いま、生きているんだから、
そうだろう。
違うか?
生きてるも死んでるもない。
遊べ。
どこまでもでかい宇宙とともに遊べ。
無限の遊びがここにはある。
退屈なんてしている暇はねえ。
殺しあってる暇はねえ。
死を望む暇はねえ。
そんなものは糞食らえ。
そうやって、
天球の空、
無限の空白を貫くんだ。
なにもないところに、
風穴をあけるんだ。
暗い暗い底なし沼のような部屋の、
見えない底に、
穴を穿つんだ。
打て。
打て。
打て。
うつことがうたうことだ。
そうすれば穴があく。
地下室の底にも穴があく。
そしたらそこには、
無限の青。
穴の底には、空がある。
だから空という文字の上には穴があるんだ。
だからどこへでもいける。
うたえ。
おまえのうたをうたえ。
切り取られた境界線、
無数に引かれた線描、
それらが囲い込むあらゆる面、
それが部屋の壁だ。
壁にあけるために、
うたえ。
壁など初めからそこにはない。
誰かが、勝手に造っただけだ。
だから、
穿て。
壊せ。
生きることが壊れゆくことならば、
壊してくるものを壊せ。
穴をうて。
そして新たにそこにつくれ。
境界線などないのだと、
直線都市などないのだと、
俺たちはあまねく俺たちの窓なのだと、
穴を穿てば、そこは窓になるのだと、
そう、信じるんだ。
それが、意志。
それが、種。
アスファルトの地面を突き破って、
空に向けて咲く一輪の花。
おまえはそれだ。
俺もそうだ。
それが、意志。
それが、種。
はじめから決まっているんだ。
それは種に宿っているのだから。
でも、
それでいて、
完全に自由だ。
アスファルトの地面の下に植えられた種が、
アスファルトという線を突き破ってはいけない理由などどこにもないのだから。
それを自由と呼ぶ。
それを自在と呼ぶ。
あらゆる境界を貫く光がある。
それが、意志。
それが種の道筋。
道はそこに産まれる。
はじめから決まっているけれど、
そのはじめは、
何度でもはじめからはじまる。
女の右腕に引かれた真っ赤な血のように。
それは何度でもはじまる。
だから、自由だ。
はじめから完璧に決まっていることと、
だから完全に自由であることは、
同時にうまれるんだ。
運命と意志。
それらは分けられない。
それらは卵子と精子。
ひとつになるからそこに自由がうまれる。
おまえがおまえでいいのだとなる。
そうあるのだとある。
星々が煌めく。
神意と人意の一致するゼロポイント。
完全な重なり。
そこに種があり、
そこに卵があり、
そこに島があり、
そこに鳥がおり、
そこに俺やおまえがいる。
うまれる。
何度でも。
はじめから。
だから苦しむ必要なんてない。
うたえ。
そして、
笑え。
貫けば、
ほら、
無限の空。
そこにはなにもない。
そして、すべてがある。
だから、播け。
無限の種を、
空にむけて。
境界線上にネロはいない。
それは問い続ける。
そして線を消していく。
だからそこには線はない。
あるのは意志。
そして種。
そしてひかり。
無限の粒子と波が蠢く、
闇のなかのひかり。
コロもそれになった。
俺にとってのコロはひかり。
生きてるも死んでるもない。
なるもならないもない。
あるもないもないしある。
そんなことはどうでもいい。
歩け。
おまえの道を歩け。
道なき道を歩け。
そこに道がある。
歩くところに道がある。
急ぐこともない。
気ままにあてもなく歩く。
単なる散歩だ。
単なる散歩でいいじゃないか。
遠い旅路の果てに、
目的地はない。
歩くことだけが俺たちだ。
境界線上にネロはいない。
彼は歩いている。
歩きつづける。
いつまでも。
だからそこには、
あらゆる境界は、ない。
だから歩くのだ。
問い続けて。
境界線上にネロはいない。
みいんなのなかのネロ。
好きに歩いてゆけよ。
俺も気ままに歩いてゆくよ。
だからあなたも歩いてゆけよ。
どこかで出逢ったら、
ともにうたおう。
それぞれの線とその消失と、
交わりの地点で、
なにもないその場所で、
すべてのものと、うたをうたおう。
境界線にネロはいない。
それはいつも、
いま、ここで、
あらゆる道を、
決められた道を、
完全に自由な道を、
歩いてゆく。
何度でもはじめから。
何度でもおわりから。
歩いていく。
さあ。
もう時間だ。
歩き出さなくては。
またどこかで会う日まで、
さようなら。
またいつでも、
どこでもないここで、
この場所で、
いま、ここで、
お会いしましょう。
またいつか、
この場所で。