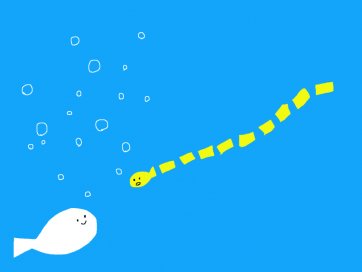トーキョーに来てもうだいぶ経ったんじゃないかとおもう。それで、わたしのトーキョーについてを書きます。トーキョーに来てから本格的に続けていることに短歌があるので、短歌についても書けたらとおもいます。ひとつの記事につき、1つか2つの好きな短歌を紹介できたら。
わたしは四国の愛媛からここに来ました。愛媛では中学生と高校生で、吹奏楽部員をしていた。夏はそのころ強烈に吹奏楽の夏でした。中学も高校も毎日が部活で忙しく、「ぜんぶ終わったら。しようね」という約束をいっぱい取り付けたものです。大会とかがぜんぶ終わったら町に出て遊ぼう。新しい漫画貸借りしよう。暇になったらあのちょっと高めのかき氷、食べに行こう。それでいて、ぜんぶが終わることなんて起こらないともおもっていた。永遠に、永遠に、永遠に、永遠に、終わらないでほしかった。そして、それでも時間は流れて、わたしは飛行機に乗ってトーキョーに来た。初めてトーキョーに来たのは大学受験のときです。そのときはおなじ大学のおなじ学科を受験する吹奏楽部の仲間である友だちと、ふたりで飛行機に乗った。よく晴れていた。こんなに遠くまで来てしまった。
「今日はどこに泊まるん?」と友だちはわたしに訊いた。「あたしは、タカダノババ」
「たかだのばば」とわたしはいちど復唱してから答える。「わたしはふつうのホテルだと思う」
乗る飛行機や泊まるホテルの手配はすべて母がしてくれていた。ありがたいことだ。わたしは友だちが泊まると言うタカダノババに思いを馳せた。ようわからんけど、民宿っぽい響きだ。友だちの口調からはそこがよく知られた場所のようにも感じられ、わりと有名なチェーン店とかだろうか。愛媛のひともよく知っているような。高田引越しセンターもタカダだもんな。そういうかんじの、ババ。気の良さそうなおばあさんの接待してくれそうな印象だけど、ババだから婆っていうのは安直すぎるか。
果たしてそこはお城と町が一体となったような絢爛な場所で、わたしは「千と千尋の神隠し」の湯屋を思い出す。インターネットでわくわくしながら眺めた外国の廃墟のことなども思い出す。町のまわりはぜんぶが夜だ。昼だったのに夜。なんだこれ。さすが都会。その夜のなかのひときわ黒い城がタカダノババなのだった。剥き出しの電球たちが、どういう仕組みで浮いているのだろう、無秩序に空中に配置され、いろんな色に光っている。わたしたちを乗せたヤマノテ線がタカダノババ駅に近づき、そのきらめきを目にしたとき、思わず「うわあ」と声が漏れた。友だちはわたしを見て少し困ったように笑い、「大丈夫、見た目だけだし。こわいことなんてなんもないんよ」と言った。タカダノババ、タカダノババデス、と電車のアナウンスが言う。友だちはその光のなかに降りた。わたしは別の駅で乗り換える。だから降りない。電車のドアが閉まって、わたしは友だちに手を振った。友だちもわたしに手を振っていた。ぎこちなく手を振りながら、おなじようにぎこちなく手を振る友だち、だんだんわたしから遠ざかり小さくなっていく友だちを見つめて、たとえば、わたしがあの子じゃないことの不思議さ、が浮かぶ。これは死んでしまったひとのことを考えるときに飛んで来る感覚に似てる。そのときわたしたちはまだそんなこと影もかたちも知らないのだけど、気づいていないのだけど、または気づいてなんかいない振りをしているのだけど、高校の吹奏楽部の仲間たちであったわたしたちは当然高校生でなくなるし、それぞれの道をゆくし、わたしたちはどうにもこうにも永遠じゃないから、もう二度と、二度とあのときとおなじみんなでおなじ演奏をすることは、ないのだった。
「またね」とわたしは言った。
「またね」と豆粒ほどの大きさになった友だちが応えるのを見た。
わたしたちはそれぞれ無事に受験を終えて、また高校であったり、違う大学だけどもおなじくトーキョーに進学したので、ときどき学祭とかで会ったり、お互いの大学卒業後には共通の友だちの結婚式で会ったりなんかする。
終わらないことが望めないのだったら、ぜんぶ覚えていたいと思う。
「あのとき、ほんとうにびっくりしたんよ」。久しぶりに会った友だちに唐突に思い出話を振る。
「あのとき?」
「初めてトーキョーに来て、タカダノババ見たとき」
「高田馬場」と友だちは復唱する。
もちろんぜんぶが嘘なので、友だちはラスボスが住んでいそうな巨大な夜の城タカダノババのことを覚えていないし、知らないし、わたしは友だちにこんな質問をしたりもしていない。
東京に暮らし始めて、最初に住んだのが下井草という西武新宿線沿いの町だった。下井草の日々のなかのひとつに、西武線の黄色い車両に乗ってぼんやりアナウンスをきいていた。次は高田馬場です、と車掌さんは言う。「さかなのパパ?」と斜め前に座る親子の、子どものほうが親のほうに尋ねるのをきいた。「さかなのパパ」とわたしはテレパシーみたいにして答えた。黄色い車両はちょうど反対色の青い青い海のなかに潜り、さかなのパパに向かっていく。
– – – – – – – – – – –
友達がぎこちなく振る両腕をすべて自分の一部と思う
/山崎聡子『手のひらの花火』(短歌研究社、2013年)
– – – – – – – – – – –