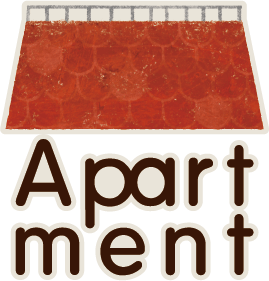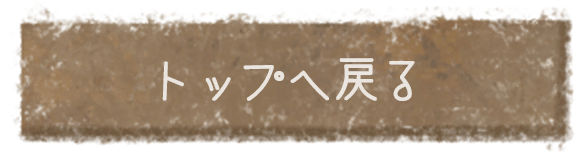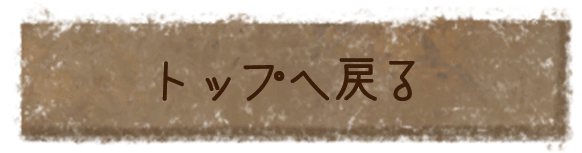僕は酒を飲まないので、嗜好的な飲みものといえば珈琲である。
先日から書いている通り、いろいろ面倒なことに直面して、他の人のように酒で気分を紛らわすわけにもいかず、やたら珈琲を消費してる。大量摂取は胃には悪かろうが、酒の依存のように他人に迷惑を振りまくわけでもないから、まぁ可愛げのある嗜好品であろう。
昔カンテ・グランデで働いていたときにバイト仲間の凝り性の何人かとで、まかない用の珈琲を誰が一番美味しく淹れられるか競っていた。店長ヤスダさんが「カマウチの淹れるのは美味い」と言ってくれたので、気をよくしてさらにドリップの技術を研鑽した。人は褒めると育つのだ。
その頃からなので、珈琲のハンドドリップ歴は35年を越えるのである。素人とはいえ歴は長い。今でもほぼ毎日挽いてドリップしては飲んでいる。
最近、焙煎豆の高品質を謳うロースターや珈琲店が増え、お金もないのでそんな多くは体験できていないのであるが、淹れているところをみるとKONOやHARIO等の円錐形のドリッパーを使っている店がほとんどである。
僕が昔から馴染んでいるのは、ドリッパーの底に穴が3つ開いたカリタ式で、ここ数年は1つ穴のメリタ式が気に入って愛用していた。しかし最近流行の円錐形ドリッパーは使ったことがなかった。
3穴カリタと1穴メリタでは滴下速度が違うので、それによって湯が豆に触れている時間が変わり、味に差が出るのは理解できる。しかし先端に大きな穴が開いている円錐式はもっと速く湯が落ちていくので、素人考えでは抽出が不十分なのではないか、と不安だった。
そこで珈琲の淹れ方と味を科学的に考察する本を改めて探して何冊か読んでみたのである。
詳しい解説はハショるが、ごくごく大雑把にまとめるならば、
(1)浸漬時間・・・豆が湯に「浸かっている」時間。
(2)透過時間・・・豆の中を湯が通過している時間。
要するに珈琲の淹れ方のバリエーションはこの浸漬時間と透過時間の組み合わせのパターンにすぎない、ということだと理解した。大雑把すぎるか。
–

(右上から時計回りに、フレンチプレス、カリタ式、メリタ式、HARIO円錐ドリッパー)
–
たとえば家庭用の珈琲メーカーやコンビニの珈琲マシーンは、ほぼ (2) だけである。ハンドドリップの「蒸らし」の工程がない。湯の滴下の速度を変えて(緩→急)多少の調節しているかもしれないが、基本、透過させるだけである。
逆にフレンチプレスは(1)しかない。急須でお茶を淹れるのと同じ方式だ。器具もないし自分で淹れたことはないけれど、原理的にはサイフォン式も同じだと思われる。
(これをもっと過激にすると、ヘミングウェイが「これが一番美味い」と豪語していた「湯で豆を煮出す」方式になる。一度試してみたが、ヘミングウェイは噓つきだ、という結論に至った。)
円錐ドリッパーは穴が大きいので、30秒の蒸らし時間のあとは速めに湯が透過される。
ドリッパーの説明書にも「杯数にかかわらず3分以内に抽出を終わること」と書いてあり、抽出後半に出てくる「雑味」をサーバーに落とさないというのが信条のようである。
1穴のメリタは逆の思想で、穴はドリッパーの底面より1段高いところに開けられており、湯がスムーズには落ちない仕掛けである。できるだけ (1)の時間を長引かせようということだ。円錐派が「雑味」と嫌う成分をもある程度包括して取り込むやりかたと思える。
たしかに高品位豆の店が出す珈琲は深煎りの豆種であってもすっきりしている。
家でも円錐ドリッパーを買って最近使ってみているのであるが、たしかに「雑味」が消える。なるほど、これは「美味しい」の一つの形であろう。
■
しかし、だからといってメリタで淹れたときの「雑味」が、僕は嫌いではないのである。雑味といえば聞こえは悪いので、味が重層的である、と言い直そう。
そう、僕は「ノイズも味」という考え方である。グレン・グールドがピアノ弾きながら歌う鼻歌はあれはあれで彼の音楽に不可欠な要素だ。たぶん和声分量的に必要と思われる場所でわざと歌っているのだと思う。キース・ジャレットもけっこう唸りながら弾くね(ただ彼の声は高音でちょっと耳に障るときもあるけれど)。
円錐ドリッパーが主流になりつつある今も1穴や3穴が滅びないのは、重層的な味が好きな層も多いということだ。複雑さも一つの正義である。「すっきり」は珈琲の美味しさの一派閥にすぎない。
昔、中国茶に凝っていた頃、100gで1万円なんていう高級凍頂烏龍茶が神戸中華街の専門店に売っていて、どうしても好奇心を抑えられず「さ、30gだけでもいいですか」と3千円分だけ買ってみたことがあった。
ドキドキしながら淹れてみると、なんとも幽玄な、微妙な、深遠な・・・ありていに言えば「・・・う、薄っ!」という感じだった。
確かに、なんだか凄いのはわかるのだ。しかしその「凄さ」が、ものすごく遠い。
「香り・味」という概念をものすごく遠くから観察するような。いや、「香り・味」というものの「イデア」を愛でるような・・・わかりそうでわからない、遠い世界なのだった。
あとで茶殻をとりだして伸ばしてみると、ほとんど枝葉の形がそのまま寸欠もなく再現された。刻むことも厭うような、弩級の丁寧さで作られていることは理解した。押し葉にして額に飾れるレベルだった(飾ればよかったな)。
ちなみに、凍頂烏龍茶は100g3千円くらいの「やや高級」あたりのものが一番(普通に)美味い、ということを、後のトライヤルによって知った。凡夫には仙境はむずかしいのだ(貴重な体験ではあったけれど)。
美味しさの純度、というと、あの高級烏龍茶を思い出すのである。スペシャルティ珈琲的「雑味なし」珈琲の行きつく先が、あのような「遠い味」に突き進みはしないかと、おせっかいな心配をしたりしている。
まぁ、多少貧乏人の僻みは入ってるのかもしれん。
要は気分の問題であるから、円錐ドリッパーで雑味の少ない珈琲を淹れ、メリタで複雑な重層を楽しみ、ヘミングウェイ方式で「ないわー」と呆れ、たまにフレンチプレスで油脂分をまとった舌触りを試し、基本に戻ってカリタで中庸を楽しみつつ昔のカンテの厨房を懐かしみ、たまには高い店で「へぇー」と流行の動向を知り、年一回くらいは高い豆を買い(もっと頻繁に買いたい 涙)、業務スーパーの安くて美味しい珈琲豆に感謝し、ときにコンビニ珈琲で息継ぎし、ネスカフェエクセラを残業仕事の燃料にし、日々珈琲で憂さを晴らして生きていくのだぜ。やー。