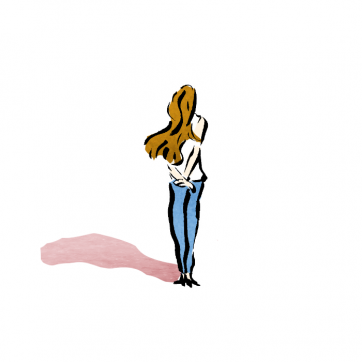
雨上がりの秋葉原は、酷く蒸していた。まるでサウナだ。時刻は零時前で、終電を捕まえようとする人達がぞろぞろと駅に向かっていく。僕はその流れに逆らい、末広町へと向かう大きな道を進んだ。
ベッドに入ったのが八時。眠るにしては早すぎる時間だったけれど、それ以外にすることがなかった。眠りに落ちる直前、雨が降りだした。守られているような、それでいて自分の孤独を思い知らされるような、静かな雨音だった。
目が覚めると吐き気がした。薬のせいかもしれない。背中に嫌な汗をかいていた。僕は重い身体を引きずって台所へ行き、水を飲んで壁にもたれかかった。またすることが無くなってしまった。腹は減っていなかったし、またすぐに眠れるとも思えなかった。ついでにこの頃、性欲も無かった。無理に自慰を試みても途中で嫌になった。自分は何て虚しい生き物に成り下がったのだろう。何もできない。何かをしたいとも思えない。まるで人形だ。いや、人形以下だ。もっと面倒な、醜い何かだ。
僕はもう一杯水を飲むと、柔らかいシャツに着替えて表に出た。部屋にいるより、外に出たほうがいいような気がした。
外は晴れていた。部屋を出て十五分も歩くと、無数の眩しい看板たちが僕を出迎える。居酒屋、ラーメン屋、蕎麦屋。どこも営業しているけれど、長居できる場所ではない。最初はふらふらと歩くだけのつもりだったけれど、あまりの蒸し暑さにすぐ疲れてしまった。額から、首から、汗が流れ落ちる。僕は道を引き返し、何度か行ったことのある漫画喫茶に入った。
漫画喫茶は奇妙な空間だと思う。たくさんの人が仕切りの中で好き好きに過ごしているのに、とても静かだ。話し声はしない。携帯電話の音も滅多に鳴らない。薄気味悪いくせに、どこか居心地がいい。僕はドリンクコーナーで烏龍茶をもらい、雑誌コーナーにあったものを適当にとってラウンジのソファに座った。周りは空いていた。この時間だと大体の客は個室に入って仮眠をとる。
雑誌を開くと、文字の小ささに驚いた。脇に置いて、週刊誌を取る。漫画だって内容はろくに頭に入ってこないけれど、絵面を見ているだけで気は紛れた。時間をかけて短い台詞を読んでいると、隣に誰かが座った。ふわりと甘い匂いが漂った。
相手は若い女性だった。明るく長い茶髪をしている。席はがらがらに空いているのに、彼女は僕の隣に座っていた。本も飲み物も持っていない。僕は落ち着かなくなった。
「話しかけてもいいですか」
僕は念のため、周りに僕以外の人間がいないことを確認して、彼女のほうを向いた。前にもこんなことがあったような気がした。どこで?そうだ、寿司屋だ。
「どうぞ」
僕は少し警戒しながら頷いた。
「いきなりごめんなさい」
彼女は雑誌のモデルのようにはっきりと濃い化粧をしていた。目の周りは黒いアイラインで囲まれ、口紅は鮮やかな赤色だ。僕はあまり化粧の濃い女性が好きではない。甘ったるい香水の香りも。
「困ってることがあるんですけど、チャットで相談してもいいですか」
「チャット?」
彼女は壁際に並んだパソコンを指差した。
「お願いします、五分くらいで済みますから」
彼女の瞳はどこか切羽詰まっていた。こんな平和な漫画喫茶で、何を困ることがあるのだろう。訝しがりながらも、僕はとりあえず頷いた。
「いいですよ」
僕達はパソコンを利用できる席に移ると、大型のチャットサービスにログインして二人で会話できる部屋を作った。
彼女は素早くキーボードを叩き始めた。
『個室の部屋に移れるよう、私の代わりに受付で利用プランを変更してもらえませんか?お金はもちろん払います』
僕はぱたぱたとキーボードに返事を打ち込んだ。
『構わないですけど、自分で行けない事情があるんですか?』
『人に追いかけられているんです。受付で並んだら、相手が入ってきたときに鉢合わせしてしまうから』
追いかけられている。その言葉の物々しさに驚いて、僕は周囲をさっと見回した。挙動不審な人間は見当たらない。
『誰に?』
『事情は後で詳しく話します。とにかく今は個室に隠れたいんです』
僕は一瞬、彼女が僕を騙して害を及ぼす可能性について考えようとした。けれど僕の頭はろくに働かなかった。
『わかった』
『ありがとう』
彼女は見るからに高級そうなブランド物のバッグから赤い長財布を取り出し、一万円札を抜き取った。僕はそれを受け取った。
「会計が終わったら鍵を持って、トイレの前まで来てくれませんか。ノックしてくれれば開けます」
頷きかけて、僕はふと思い留まった。
「ここのシステムだと、部屋に入る人間はIDをチェックされるんじゃなかったかな。君は結局、君が受付しないと個室に入れないんじゃないか?」
彼女ははっとした顔つきになった。
「どうしよう」
彼女はしきりに受付の方向を見始めた。
「僕が店員に事情を説明してみようか。なるべく周りの人に聞こえないように。その間に君はトイレに隠れるっていうのはどう?」
彼女は頷いた。
「お願いします」
彼女はお辞儀すると、足早に去っていった。バニラの匂いだ。僕は彼女が去ってから、ようやく香りの名前を思い出した。
僕は席を立って、雑誌と週刊誌を返却し、受付に並んだ。妙なことになったと思った。時折店に入ってくる客に目をやった。終電を逃したであろう大学生やサラリーマンが何人か現れたけれど、誰かを探す素振りをする人間はいなかった。誰もが疲れていて、とりあえず座るか眠るかしたがっているように見えた。
彼女は何から逃げているのだろう。ストーカーだろうか。もし刃物を振り回すような輩だったらどうなるだろう、そんなことを考えていると運良く女性の店員が歩いてきた。僕はとっさに列を外れて、彼女を呼び止めた。
「すみません、ちょっとご相談したいことがあるんですけど」
彼女ははい、と言って足を止めた。僕は声を落として、事情を簡潔に説明した。店員は驚いた表情をしていたけれど、冷静に話を聞いてくれた。
「そのお客様のお名前を頂戴できますか?」
僕はしまったと思った。名前は聞いていない。お金だけを渡されたのだ。
「すみません、聞きそびれました」
「わかりました。私が代わりにプランの変更をして、その女性に部屋の鍵を渡しに行きます」
「助かります」
お金を渡すと、彼女はレジ裏でてきぱきと処理らしきものを済ませ、薄暗い店内の奥へと消えていった。
パソコンの利用席に戻ってチャットルームを見ると、彼女は部屋にIDを残したままだった。僕は試しに話しかけた。
『大丈夫だった?』
返事はない。僕は新しく取ってきた雑誌をめくった。前回の反省を活かして、写真の多い旅行雑誌にした。烏龍茶の氷はすっかり溶けて、まるで水のようだった。僕はそれを機械的に飲んだ。
『無事に個室に入れたわ。ありがとう』
彼女から返信が返ってくると、僕は雑誌を閉じて横に置いた。
『女の店員さんが来てくれたから助かった。一番奥の部屋にしてくれたの』
『それはよかった。女の人のほうが良さそうな気がしたんだ』
『本当にありがとう。すごく助かったわ』
『でも、もし君を追いかけているのがまずい奴なら、警察を呼んだほうがいいんじゃないかな』
『まずい奴というか、昔の恋人なの』
僕はあまり驚かなかった。よくある話だ。
『でも逃げないといけないような事態なんだね?』
『私にもいけないところがあるの。別れようってはっきり言えなくて・・・。今夜もここで待ち合わせる約束をしたんだけど、嫌になって断ろうとしたら相手が怒って、無理やり会いに行くって言い始めたの。私は帰るってさっきメッセージを送ったから、諦めてくれたと思うんだけど』
僕は溜息をついた。どんな事情であれ、女の子が男に追いかけられて夜を過ごすなんて心細いに違いなかった。
『他に僕ができることはある?』
『ううん、もう充分。本当にありがとう。でも眠れそうにないから、落ち着くまでチャットしても良い?』
僕は微笑んだ。不眠仲間だ、と思った。
『僕も眠れなかった』
僕達はお互いのことを自己紹介した。彼女は大学生で、僕の印象通り、モデルのアルバイトをしていた。
『モデルってどんな仕事をするの?』
『簡単よ。綺麗な服を着て、ポーズをとるだけ。でも時間がかかる割にお給料は安いし、大学も忙しくなってきたし、そろそろ辞めるわ』
『ここの漫画喫茶にも君が載ってる雑誌があるのかな』
彼女は笑顔の顔文字を送信してきた。
『きっとあるわ。Xっていう雑誌で、先月載せてもらったの』
『後で探してみるよ』
女性のファッション誌を読むのも気分転換になるかもしれない。よく考えたら一度も手に取ったことがなかった。
『せっかく雑誌に載るようなモデルなのに、辞めて後悔しないの?』
『刺激的だったことは確かだけど、良いことばかりじゃなかったわ。競争は激しいし、モノみたいに扱われることもあるし。モデルをしているっていうだけで、面白がって寄ってくる人たちもたくさんいた。そういう人たちの相手をするのが一番疲れたの』
僕は苦笑した。
『僕の周りにも、似たようなことを言う奴がいたよ。うちの勤め先はそこそこ有名だからね。勤め先の名前を出すと女の子たちは寄ってくるけど、趣味の話を始めるとしらけた顔をされるってさ」
『それ、すごくよくわかるわ。どこにいっても似たようなことはあるのね』
そのときだった。店員が「受付はお済みですか」と誰かに話しかけるのを聞いた。僕は振り向き、次の瞬間に後悔した。声をかけられていたのは十中八九、彼女の元恋人だった。日焼けした、がっちりとした体格の、きつい目をした男だった。男はこちらのラウンジをじっと見ていた。僕はゆっくりと画面に向き直り、熱心にインターネットをしているふりをして耳をすませた。
男は店員に向かって「なんでもないです」と言い、去っていった。あんな男に追いかけられたら、僕だって怖い。僕は今起きたことを、彼女に言わないことに決めた。
『ねえ、どうして今夜はここにいるの?終電を逃したの?』
僕は彼女との会話に集中することにした。
『眠れそうになかったから、時間をつぶしにきたんだ』
『恋人はいる?』
『いない』
沈黙。
『ねえ、こっちの部屋に来ない?』
僕はどきりとした。
『個室には申し込んだ人間しか入れないよ』
『二人で入れる部屋に移動すればいいと思う』
彼女と薄暗い部屋で過ごすことについて、僕は肯定的な気持ちになれなかった。
『やめたほうがいい』
『どうして?二人でいたら眠れるかもしれない』
『それでも今夜は、一人で眠ったほうがいいんじゃないかな。あまり年上ぶった忠告はしたくないけど、知り合って間もない男を隣で眠らせるのは良くないと思う』
彼女はしばらく何も言わなかった。僕は二人でいたら眠れるかもしれないよという言葉を眺めて、胸がひっかかれるような思いがした。
最後に誰かと眠ったのはいつだっただろうか。
『わかった。ごめんなさい』
『謝ることはないよ。誰かに追いかけられたりしたら、心細くなるものだと思う』
『ううん。あなたと話したら落ち着いてきた』
『よかった』
その後の沈黙は長かった。僕は雑誌を一通りめくり、空になったグラスに新しい飲み物を注ぎに行き、席に戻った。
『おやすみなさい』
僕はその言葉には返さず、目を瞑って深呼吸した。彼女が眠れますように、と僕は祈った。もし眠りの神様がいて、何かを課すために僕から眠りを奪っているのだとしても、彼女の穏やかな眠りを願う権利くらいは残っているはずだった。きっと。
<続く>

挿絵協力:keitoさん



