目の前の暗い地面から潜水艦のようにせり上がった黒い小さな楕円体が急に地面からちぎれて駆け去った。
あわてて自転車をとめて行方を目で追うと、小さな小さな黒猫だった。
あまりに小さいので猫らしくなくて、まるで機械仕掛けの偽猫のようだったが、地面からちぎれて出現したのと同じように、道路脇の茂みに溶けて消えた。
◆
新撰組の沖田総司が肺結核で隊を離れ、知り合いの植木屋で療養生活を送っていたとき、庭に毎日黒猫が現れるので、沖田は刀を持って庭に出て斬ろうとするが斬れず、猫も斬れなくなった自分を嘆いて失意のうちに死んだ、云々。
そんな話を読んで、まぁ人間でもざんざん斬り殺してきた沖田総司ではあるけれど、猫も庭に出現するくらいで斬り殺されてはたまったもんじゃないなと思った。
浮世絵なんかを見れば愛玩動物として美女の側に描かれたり、または妖怪に変化して怪異譚の主役を張ったり、江戸時代でも猫はそれなりの存在感を持って人間の側に暮らしていたようだが、しかし一方で、庭を横切ったくらいで沖田総司に斬られそうになったりする、軽い存在でもあったのだと思われる。
猫をかん袋に押し込んで、ポンポン蹴り遊んだ山寺の和尚の歌があるが、そんなことをすればもちろん「にゃんと鳴く」どころか猫は複雑骨折の上死んでしまうだろう。
この歌の元歌(ぽんにゃん節)は「猫を紙袋に入れてちょっと押せばにゃんと鳴く」といったソフトなものだったらしいが、「童謡」に昇格したころには鞠代わりに蹴られる歌になっていた。真に受けて真似して猫を死なせてしまったバカもいただろう(何だったか、そんな小説を読んだ覚えがある)。
長屋の軒下に猫が子供を生んで、おかみさんが「うるさいったらありゃしない」とか言ってバケツの水に子猫を漬けて始末する、みたいな場面も何かで読んだ。ふつうに、当たり前に行われてきたことなのだろう。
昔から人間に愛される一方で、びっくりするくらい軽々しく扱われてきたのも猫である。
昔の人は酷いとか、そういう話ではなくて、保健所で殺処分になる犬猫の数のことを考えると、彼らは今も軽々しく扱われていることに全然かわりはないのであって、沖田総司や長屋のおかみさんが直接手を下さず、見えないところで始末されるようになっただけなのだ。
◆
先月も書いたように、僕は高校の頃新聞配達のアルバイトをしていたのだが、ある日、早朝ゴミ捨て場に(まるで漫画みたいに)段ボール箱に入った、黒い子猫が一匹だけ捨てられていた。
可哀そうに思い、いろんな猫を保護して里親を探したりしている「猫おばさん」に心当たりがあったので、あとで彼女のところに持って行って相談しようと思ったが、とりあえず今は僕は新聞を配らなければならない。少しでも遅れると門の前で仁王立ちで配達を待っているおじさんとかも区域内にいて、そのおじさんの舌打ちを聞くのが毎朝プレッシャーだったのである。
まずは新聞。猫はそのあとだ。
思いついたのは、近所にあった、とある(新興)宗教を熱心に信仰しているという噂のおばさんの家だった。信仰心に篤い人ならば子猫をムゲには扱うまい。
僕はその「信仰おばさん」の家の庭に箱ごと子猫を押し込み、「ちょっと待ってろよ~」と言いながら配達に戻った。
配達が終わって急いで戻ると、信仰おばさんはホースを持って庭に立っている。
嫌な予感がして探すと、門の外にびしょ濡れの子猫がぶるぶる震えてうずくまっていた。箱から這い出して庭にいたところを、ホースの水で門外に追い出されたらしいのである。
怒りを覚えたが、ぐっとこらえて子猫を拾い上げ、信仰おばさんの家をあとにした。悪いのは「信仰心に篤い → 動物にも優しいに違いない」という自分の浅はかな思い込みの方である。仏教系なら森羅万象生命は大事、みたいな考えもあろうが、おばさんの神様は多分人間しか扱ってくれず、猫は水をかけて追っ払うがよい、とでも教典に書いてあるのだろう。
猫おばさんは子猫を気前よく預かってくれ、二人で信仰おばさんの悪口を言い合ってウサを晴らした。
そのとき、子猫を乾かしながら、濡れて張りついた黒い毛の間から子猫の耳の穴を見た。
小さな頭蓋骨の奥深くへ、子猫なのでおそらく相対的に大きいと思われる耳の穴が、無限の深さで続いているように見えた。
深い穴から脳まで見えるのではないかという恐れで(見えるわけないが)、今まで可愛かった子猫が一瞬おそろしいものに見えてしまった。
「猫の耳って、見てたらなんか怖いですねぇ。吸い込まれそう」
と猫おばさんに言ってみたら、きゃっきゃと笑って
「この子の頭に入ってこの子の目から世界を眺めてみたいねぇ」
などと猫おばさんはファンタジーなことを言うのだった。


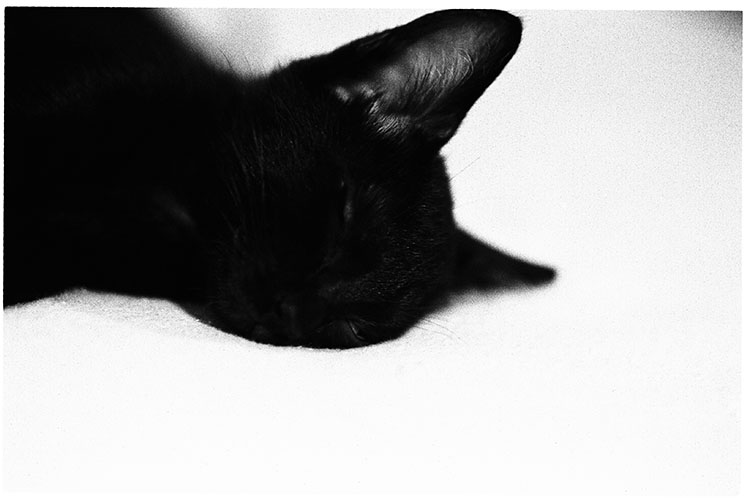



(2005 「夏生さん家の猫」)
*文中の猫ではありません



