
ここまで「場の詩プロジェクト」の各企画意図についてあれこれ書いてきたけれど、「実在しない恋人カフェ」という企画に関しては、とくに深い意味はない。ただわたしが”恋バナ”をしたかっただけだ。私利私欲。
恋バナ=恋愛の話をするのはむずかしい。というとふしぎそうにされることもある。しかしこんなにむずかしいことはない。恋愛といえばなんとなく響きはいいがようは性愛であって、そんなパーソナルな話ができる相手はそうそう見つからないし、人から聞き出そうにも気をつかう。
またパーソナルな話題であるがゆえに、常識として共有できる前提が少ない。恋愛について知識として知っていることがいくらあっても、恋愛そのものがじっさいにあらわれるのは恋愛のシーン、つまりは恋愛関係にある当事者しかいないクローズドなシーンでだけだ。もしカップルと交流したとしても、その人たちがふたりでいるところを観察することはできない。逆に、自分と恋人がふたりきりでいるところを誰かに見せたり、そのうえで査定してもらったりすることも、当然できない。
そうなると、これは当然恋愛の常識でしょう、というところが、実は人によってかなり大幅にずれている、という可能性が出てくる。やっぱり、”恋バナ”はかなりリスキーな遊びではないか。自分がどれくらい異常か確認しづらい部分、かつ性愛に近い部分を、他人に対してさらけだすなんて……(「えっ、連絡は月に一回くらいしかとらないのがふつうじゃないの?」「えっ、『はじめて会った日』を記念日にするのがふつうじゃないの?」)
……と、いろいろ御託を並べたけれど、結局のところはわたし自身が友だちも恋愛経験も少ないために「恋バナ」とは縁遠く、でもやってみたい、というだけだった。恋バナはリスキーでおそろしいが、同時になんだかめちゃくちゃ楽しそうでもある。「どこが好きなの?」とか、「どこで知り合ったの?」とか言ってみたい。パーソナルな話を複数人でぱかぱか明るみに出すような関係性にもあこがれる。
◆
ということで、その日の「しょぼい喫茶店」では、「実在しない恋人」の話をしてもいいことにした。
恋バナというものが持っている重大な要素に謎の特権性がある。恋愛となんらかのかたちで関わっていないと恋バナはしづらいわけで、それがリア充だとか非モテだとかインセルだとかのちょっと偏った価値基準と結びつきやすい。恋バナをできる人(あるいは「すぐれた恋バナをできる人」)のほうが上で、そうでない人は下なんてばかばかしいのに、ただ恋バナをテーマにするだけではそういう感覚が呼び起こされかねない。それは避けたい。わたし自身も含めた恋バナと縁遠い人たちでも恋バナを単なる遊びとして楽しめるためのお題が、「実在しない恋人」だった。
「いま、付き合ってる人とかいるんですか?」
それが合言葉になった。はじめはわたしが、そのうちにお客さん同士で、なにげなく問いかける。すると、聞かれた人が口をひらく。
「あ、一応いますよ」
「えーっ! どんな人なのか聞いてもいいですか?」
その話をしにきているんだから聞いてもいいに決まっているがここは小芝居をする。
「はい、あの、いちおう彼女は既婚者なんですけど……」
「ええっ」
「でも不倫というわけではないんです、離婚届を出していないだけで別れてはいるみたいで……というか、彼女の戸籍上の旦那はいま刑務所にいるので……」
「ええっ」
もう、やりたい放題である。作り話なので何を言ってもいい。ちなみにこの話をしてくれたお客さんは壮年の男性だった。みんな寄ってたかって質問をする。
「そんな方とどうやって知りあうんですか」
「雨の日に僕が車で彼女の服に泥をかけてしまって……」
「どういうデートをするんですか?」
「彼女が団地に住んでいるので迎えに行ってドライブすることが多いですね」
「団地に……」
あらかじめ作ってきた話を聞くのもおもしろいが、こうしてその場の問答で詳細が組み立てられていくのもおもしろい。とっさの受け答えに浮かびあがってくる恋愛像はみょうに生々しく、なにかしらの実感がこもっている。最近受けた即興演劇のワークショップにも近いかもしれない。
ずっと聞き役に回っていた女性に、他のお客さんが「どんな方と付き合ってるんですか?」といきなり振る。すると、その人は一瞬目を宙に泳がせたあと、「……トイレのドアを、しめてくれないんです」と答えた。これにはみんな声をあげた。この実在感。匠だ。
そのうち、
「ちなみに、くじらさん(わたし)はいま付き合ってる人とかいるんですか?」
当然こうなるので、わたしもなにも準備せずに話しだしてみる。
「いますよー、あんまり口外してないんですけどね」
「いくつくらいの方なんですか?」
「えっと……五十代前半です」
「えー! どこで知りあうんですか?」
「大学の教授で、女性なんですけど、わたしが口説いて……」
話してみると高揚し、ちょっと照れくさい。会話のリズムにあわせて反射的に答えていくと、自分の願望や好奇心が気やすく前面に出てくる。話しているのは根も葉もない話だが、わたしが女性も性愛の対象としていて、かつ、大学教授と不倫した女子大生が「先生となら世界征服できそう」と書いていたらしい……というニュースを印象的に覚えているのは事実だ。不倫の是非はさておき、わたしも「この人となら世界征服できそう」とは思ってみたい。そういう意味では、パーソナルさを完全に退けることには失敗している。
でも、悪い気はしない。作り話のなかになんらか事実が混じっているのは、例の実体感によってお互いになんとなくわかる。でも、どこが事実なのかは最後までわからないし、べつにどこであってもかまわない。それがちょうどよいスリリングさを生んでいたと思う。
ある程度以上おとなになっても、自分について話したり聞いたりしたいとき、空想に助けてもらうことが必要なのかもしれない。でもひとりで空想するのにはスタミナが要る。そこへだれかの質問が飛んでくると、それが梯子になってくれる。会話のなかで「実在しない恋人」像を完成させていくとき、実際には自分自身を語る言葉ができあがっていく。それを、おたがい無責任に、けれど目をかがやかせて聞きいっている。空想でもって表現することのおもしろさが、「実在しない恋人カフェ」にはあふれていた。集まっているのが、おそらくいくらかシャイで、かついくらか他人が好きなおとなたちだったから、なおさら。
……と、いろいろ御託を並べたけれど、大元はやっぱり私利私欲なので、わたしは何十回も「どこで知り合ったんですか!?」「どういうところが好きなんですか!?」と聞きまくれてとにかく楽しかった。わたし自身の恵まれない青春の通夜のような場に付き合ってもらっただけという気もする。そもそも「場の詩プロジェクト」全般に、「わたしが考えた遊びをみんなにいっしょに遊んでもらいたい」というしょうもない欲求が隠れているのをここで告白しておきたい。
◆
「いま付き合ってる人とかいるんですか?」
「はい!」
と、みょうに元気よく答えた若い男性。彼は質問を待つこともなく、ひとりですらすらと「実在しない恋人」について語りはじめる。
「同い年で、同性なんです。幼馴染なので小さい時からずっと親友みたいに育ったんですけど、高校のときに向こうから告白されて付き合うことになりました。だからもう付き合ってけっこう経ちますね。小中高とずっと同じ部活で、ポジションは……」
みんなおもしろがって聞いていたが、わたしだけはひそかに息をのんでいた。
彼は、前にもしょぼい喫茶店にお客さんとして来てくれたことがある。そして、他のお客さんがいなくなってわたしとふたりになったタイミングで、同じ人の話をしてくれたことがあるのだ。ただし、その日は「実在しない恋人カフェ」ではなかった。
そのときわたしが聞いたのは、「ずっと片思いしている好きな人」の話だったのだ。
「男同士だし、告白されたときは自分の片思いだと思ってたので、めちゃくちゃうれしかったですね。自分は東京の、その人は地元の大学に進学したので離れちゃったんですけど、でもいまもすごい仲良しです。はやく会いたいです。いっしょに暮らしたい」
「事実」を知っているのはわたしだけなので、みんな彼の迷いのない語りぶりに盛り上がっている。いや、「実在」はするのだから迷いがなくて当然なのだ。本当は「恋人」でないだけで……こうなるとちょっと心配になってくる。今はいいとしても、家に帰ってひとりになってからへんに落ち込んだりしないだろうか。
と、
「その人のどこが好きなんですか?」
質問が飛んだ。
「実在しない恋人」の話をしている人によくみられる仕草として、質問を受けてから「えーっと」といって考えだす、というのがある。やってみてもらうとわかると思うけれど、「どこが好きなんですか?」というのはその中でもわりにむずかしい質問で、みんなだいたい「えーっと、自分の好きなことに夢中になっているところですかね」とか、「えーっと、意外とタフなところですかね」とか答える。ここでもやけに生々しい具体性が出てきがちなのがおもしろい。
しかし、彼はちがった。
「全部です」
即答だった。
「本当に全部が好きです」
具体性を冷やかす気で待機していた一同はなんとなく気圧される。わたしはもう、なにも言わずにおののくしかなかった。事実は、事実は、なんておそろしいんだろう。
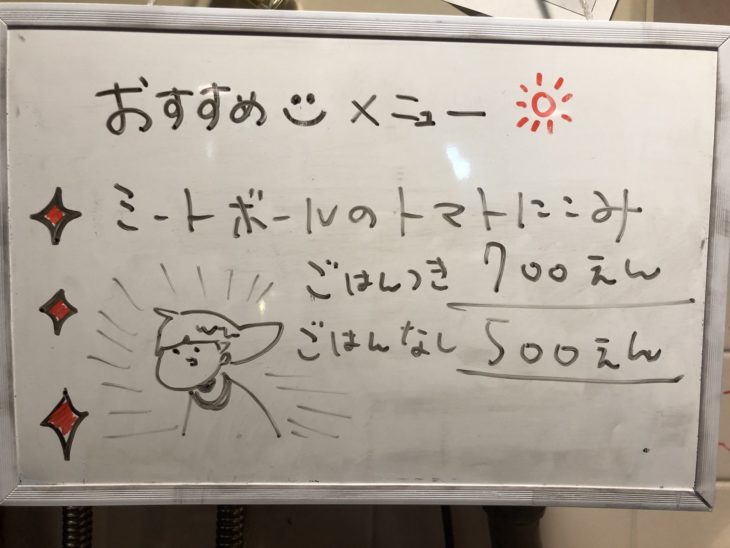
(※最後のお客さんの話だけプライバシーとアウティングの問題に配慮して少し内容を変えています。他の「実在しない恋人」の話はできるだけ話されたまま書いています)


