まだ輸入盤店という存在を知らない頃、外資系の大型CDショップに足繁く通っては、Pop Bizというシールが貼ってある輸入盤を探して買っていた。当時はレーベルという存在すらよく分かっていなかったので、このシールを目当てに買っていけば当たるだろうという、新しい音楽を探す1つの手がかりとなっていた。Pop Bizはレーベルであり、インディ系のロック&ポップのレコードをディストリビューションしているところだった。そしてインディポップと呼ばれる音楽は、スペインやドイツ、ノルウェー、フィンランドなど、イギリスやアメリカだけではない国にたくさんのバンドがいることに衝撃を受けた。そしてそれぞれの国自体に興味を持つということにも繋がっていった。
国自体に興味を持つ、などという発想が高校時代の自分にある由も無く、だから弁論大会のテーマが「国際化」であったときは本当に呻吟した。今思うとぞっとする話だが、半分以上を顧問に書き直され、それをそのまま読み上げたのだ。いや、読み上げたのではなく暗記したのだ。人の文章を暗記し自分の言葉として発表する事に、何の疑問も疚しさも感じなかったのだから情けない。それでいて壇上に上がったときは、YMOの最後のライブのようだと前髪をかきあげながらうっとりしていたのだから気持ちが悪い。講評で「きみは俳優にでもなったほうがいい」と痛烈な皮肉を言われたのは当然の成り行きだった。先輩は論文の最後で「わたしは建築家になります!」と突如宣言した。
CD世代にとってのレコードというものは、言わば未知のプロダクトであり新鮮だった。「とにかく何でもいいからレコードが欲しい」という衝動にかられ、レコードショップのポップに書かれた「120%オリーヴギャル向け」という推薦文を頼りに買ったのはスペインのLe Mansというバンドだった。ターンテーブルにレコードを乗せ、針を落とし、聞こえてきた音に一瞬で虜になった。もちろん当時はその曲がArchie Belle&The DrellsのTighten Upネタであることなど分かるはずもなく、ただただ純粋に曲そのものに感動していた。そしてここから「レーベル買い」をするようになり、一気にレコード熱が高まるのであった。
熱が高まって車の中のカセットがグニャグニャになった腹の立つ思い出。放置した犯人は父親だ。サザンオールスターズの歌詞カードをほぼふたつ折りにしたのも許せない。音楽には妙にこだわりがあるくせに、家族旅行でのカセットのチョイスなどは人任せだった。ダムに行くときもいろいろ言われてチャゲアスになった。90年代の曲を聴きたかったのに、シングルを全曲入れたテープを持ってきてしまった。デビュー曲から延々続くネットリとした演歌調。SAY YESにもダムにも辿り着くことなく、家族全員車酔いした。
スウェーデンのバンドなのにそのCDはドイツの小さなレーベルから出ていた。店頭で見かけたことがなかったので、店員に聞いて取り寄せてもらうことにした。どれくらい時間がかかったのか忘れてしまったが、手に入れるまで2ヶ月近くかかったはずだ。入荷の電話が来て、新宿のヴァージン・メガストアに行き、頼んだCDを受け取った。「ずいぶんとお待たせしてしまったお詫び」として、ディストリビューションをしているレーベルからコンピレーションCDやフリーペーパーなどのオマケまで頂いた。この「インディ・レーベル」というものはこんなにも人の繋がりを大事にしているということに感激した。
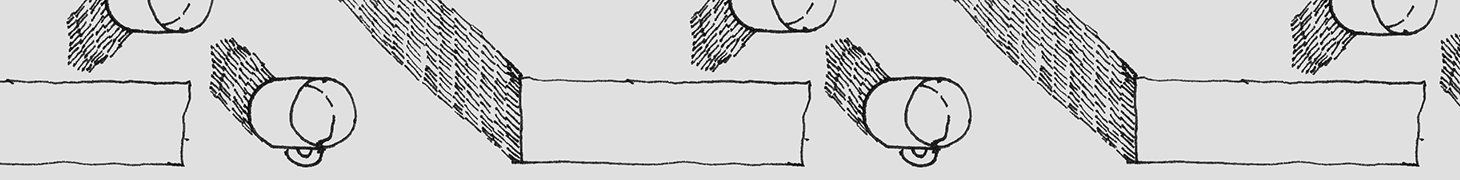
人の繋がりを大事にしていたら祖母はもっと名のある民謡の先生になったのではないか、と時々思う。祖母から聞かされるお弟子さんたちへの愚痴は、齢をとってもこんなことで人は悩むのか、という感慨を十代の自分に与えた。お弟子さんも上手い下手があって、いっつも同じところで閊えていたのは斉木さん。3階の稽古場から同じ節回しが何度も何度も聞こえてきて、その度斉木さんだけ違う。祖母が痺れを切らしている様子がありありと浮かぶ。斉木さんは太鼓も下手だった。だけど、居間で微かに聴いていた歌や太鼓の調子はずれな繰り返しは、自分にとっては心地よい思い出なのだ。泣いてしまうくらい心地よい思い出なのだ。
洋楽に興味を持ち始めた中学生の頃、イギリスからギャルっぽい女の子2人組、シャンプーが日本で大ヒットした。例に漏れず自分も彼女たちのアルバムを買った。蛍光ピンクのカラートレイが色鮮やかな輸入盤。2人のぶっきらぼうな歌い方、可愛らしくてポップでキャッチーな曲たち。シングルだった「Trouble」だけでなく、アルバム全体で満足していた記憶があるが、周りから「えっ、シャンプ~なんて聴いてるの?」と小馬鹿にされ、人に言われたことにすぐ感化される単純な自分は、彼女たちに対してどんどん冷めていってしまった。もちろん世の中的にも一発屋的な扱いで泡となって消えたが、セイント・エティエンヌがやっていたレーベル、Icelinkからシングルを出していて、実は「そっち側」の人達だったことを知るのは、ずいぶん後になってからだ。
「そっち側」とか「あっち側」とかいう発想でものごとがうまく行くはずがない。丸川くんはいい友達だと思っていたし、初恋の相談なんかもしてくれた。ただふたりで普段話すことは「スクール・カースト」についてが多かった。マウンティング覚えたての小6が「そっち側の奴ら」「あっち側の人達」と振り分けて楽しんでいたのだから、最悪の形で「大人の階段上る~」ふたりだった。転機が訪れたのは、誤解が元のけんかをした時。丸川くんは「そっち側」だか「あっち側」だか全員を味方につけた。それがどういう人達か、よりも集団であることが大事だったのだと思う。誤解が解けた後も、しばらく多くの人と喋れない状態が続いた。
「笑っていいとも」で幽霊の声が入っている曲を紹介・検証するコーナーがあった。B’zの「Risky」ネタやレベッカ「Moon」の「先輩~」は有名だと思う。そのコーナーだったのか記憶が確かではないが、大黒摩季の「あなただけ見つめてる」の中盤で聴こえる「ちんちんモミモミ」問題はクラス中で話題になった。女性コーラスの英語部分が確かにそう聴こえるのだ。昼休みの放送でかかれば大変なもので、皆静かにその部分だけを集中して聴き、毎回ゲラゲラ笑っていた。
「ちんちんモミモミ」を聴きたいがために、東田さんが持っているシングルCDを借りたのだった。小6だとまだレンタルCDの会員証も持っていなかったので、生徒同士の貸し借りが活発だった。自分はそれを見越して短冊盤はとくに綺麗に保存していて、だから東田さんからCDのトレイを真っ二つに割ったものを受け取ったときはショックだった。確かに初期短冊盤は注意書きがあるくらい「トレイは二つに割るもの」だった、とはいえ今は93年だ。ジャケットも二つ折り用にはできていない。東田さんの意外な粗雑さを一瞬思ったがそうではなく、彼女にとってはこの形状が「正しい保存方法」であり、それを律儀に守り続けていただけだ。顔の中途半端な部分に折り目の入った大黒摩季が、恨みがましくこちらを睨む。こうした不本意な風習は、94年ごろまでは各地で残存したと聞く。



