米米CLUBの「君がいるだけで」という当時の大ヒット曲を、遠足のバスの中でみんなで歌おうということになった。クラスで誰かCDを持ってる人はいないか?という話になった時、沼尾くんが手を挙げ、歌詞をコピーして配ることになった。遠足係だったぼくは彼から歌詞カードを受け取ったが、どう見ても彼の手書きだった。CDではなく、おそらくダビングされたカセットを持っていただけで、耳コピで歌詞を書いてきたのだ。サビの手前の歌詞は「True Heart」。でも彼が書いた紙には「トゥハァー」と書いてあり、見ていてなんだか恥ずかしくなってしまった。とても汚い字だったので、清書しようと思った が、どうしてもそのトゥハー部分が引っかかって筆が進まなかった。こんなものを配りたくなかった。でもぼくも当時はそのトゥハーが なんて歌っているのか正確にわからなかった。そうこうしてるうちにバスの時間が来てしまい、ついに車中で「君がいるだけで」を歌うことはなかった。
CHAGE&ASKAの「太陽と埃の中で」を遠足の車中で歌ったらスターになった。後日母と一緒に音楽の先生に呼び出されて「吹奏楽をやらないか」なんて言われたので、「自分には音楽の才能が、人目を引く才能が確かに備わっている」と思った。その後悲惨な経験(音楽の授業で責任重大なリズムパートを任され、まるで叩けないまま発表会を迎える)を経て「才能」は思い込みだったと落ち込むのだが、それはどうでもよくて、この遠足にまつわる出来事をまるで汲まずに、その後ソフトボールやら陸上競技やらをぼくに勧めてきた両親というのは一体何なのか。急に人前で歌ったりした自分を、両親は明らかに「想定外の出来事」として怖がっていた。そういう人じゃないと思われていた。
稲垣潤一の「クリスマスキャロルの頃には」という歌があった。それをノリノリで真似して歌う中村くんをみんな面白がって見ていた。今度の遠足のバスの中で、彼に「クリスマスキャロルの頃には」を歌ってもらうことにした。当日、いつものノリで真似して歌ってくれることを誰もが期待したはずが、彼は皆の前で歌うことに萎縮してしまったのか、稲垣潤一の真似どころか静かな声で、クリスマスキャロルを終始下を向いてフルで歌った。周りのみんなが彼に罰ゲームで歌わせているような、車内は賑やかではない微妙な空気に包まれた。
学生食堂略してガクショ。新校舎の向かいにあった。いや、その先の渡り廊下の辺りにあった。それも思い出せないくらい行かない場所で、そういう場所で不特定多数と接触したくなかった。まるでネクラなようだけどクラスの半分くらいはそうだったのでそういう学校だった。ガクショの厨房はおばちゃんばかりなのに、グリーン・デイの昔のアルバムがラジカセでいつもかかっていた。何となくドラマが見える。毎日ガクショに行っておばちゃんたちと仲良くなった男子たちがいて、CDを渡して、それを翌日ほんとうにかけていることに驚いて…彼らが卒業した後もそのままグリーン・デイは、大切な思い出として残されたのだ。自分とほとんど関わりのない話。
マイ・トーキョー。中野にある伯母のマンションからは、新宿副都心の高層ビル群が見える。そのうちのひとつ、三井ビルか住友ビルかで毎年クリスマスに、窓の明かりを使ってイルミネーションを作っていた。ビルの一面をキャンバスに見立て、明かりをつけた窓と消した窓で模様を作る。それを見たくて家族で毎年集まった。部屋までの階段の、小さな窓の位置が毎年変わるのが嬉しかった。背が伸びていたのだ。その成長と歩調を合わせるようにイルミネーションも年々凝っていき、ある年ついにパッと見ただけでは何だかわからないものになってしまった。楽しみにしていたぼくらは大いに失望し、家族で集まってみる習慣も途絶えた。「何だかわからないもの」の正体は、その年にソロで初来日したマイケル・ジャクスンのシルエットだった。
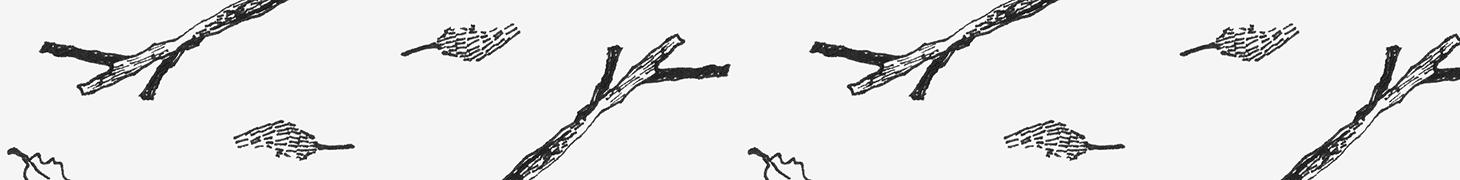
CHAGE&ASKAの「太陽と埃の中で」を遠足の車中で歌った輝かしい思い出を、もっと大事にするべきだったのだ。
初めて「自分のお金」で買ったアルバムは、彼らの92年作品「GUYS」だった。今は家電量販店になってしまった、地元のヨーカドーの2階だ。すぐに記憶から取り出せる。ブラウン管で繰り返されるPV、積み上げられたフェア棚、初回限定盤の厚み。何なら彼らが当時起用されていたパナソニックのウォークマンのCM演出だって口頭で再現できるだろう。ミュージックステーションで彼らだけ別のタイミングで登場した驚き。クリスマスには2時間の特番がテレビで組まれ、ロンドンで活動する「国際的な」様子が映る。そこから日本がいまとても裕福な国だと、小学生の自分は「当たり前に」実感する。優しい施しのように、彼らは「世界にメリークリスマス」と最後に歌う。
しかしそれらは、ずっと大切な記憶だったというわけではない。2年前の今日、思い出しただけだ。それまでずっと漠然とした、ダサい記憶の、断片でしかなかった。どうして現象は、通り過ぎると色あせてしまう運命にあるのだろう。己の思春期は「国際的な」彼らを徐々に鈍重なものと捉えさせるようになった。深すぎるエコーや「絵」にうまく結びつかない歌詞、ジャケットの袖捲りに極太ネックレス。後者ふたつへの嘲りはあまりに、ファンではない「世間一般」の目線と一致する。人気に陰りが見えた95年中頃にはもう、そうした細部が目についてしょうがないという感じだった。渋谷系、ブリットポップ、そしてテクノ。新しい「音楽の地層」が堆積される。その都度彼らは遠ざかった。当たり前に忘れた。
事件を受けてふと思い返し、彼のコード進行を洗い出したときにすべての状況が変わった。驚きしかなかった。それは新鮮なものに触れたということではない。そうではなくて、自分が気持ちいいと思うメロディや転調の法則が、ほぼそこに出尽くしていた。もう歴然と、彼らの音楽は原体験だったのだ。当たり前の事実に20年越しに直面し、同時に彼らを忘れていたことは「不当」であったと気付く。そしてこう思う。自分のような人間が何百万人もいたとしたら。その「不当」の何百万もの重なりは、はたして事件とは、無関係だったか。
彼の音楽をずっと忘れなかった人のブログに、「復帰を目指してASKAがすべきことは、”ごめんなさい”と言うこと」と書かれていて、でもそれは「ずっと忘れなかった」故の思いなのだった。ごめんなさいと言うべきは誰だろう。2年前の今日まで、ぼくは彼のことを本当に忘れていた。



